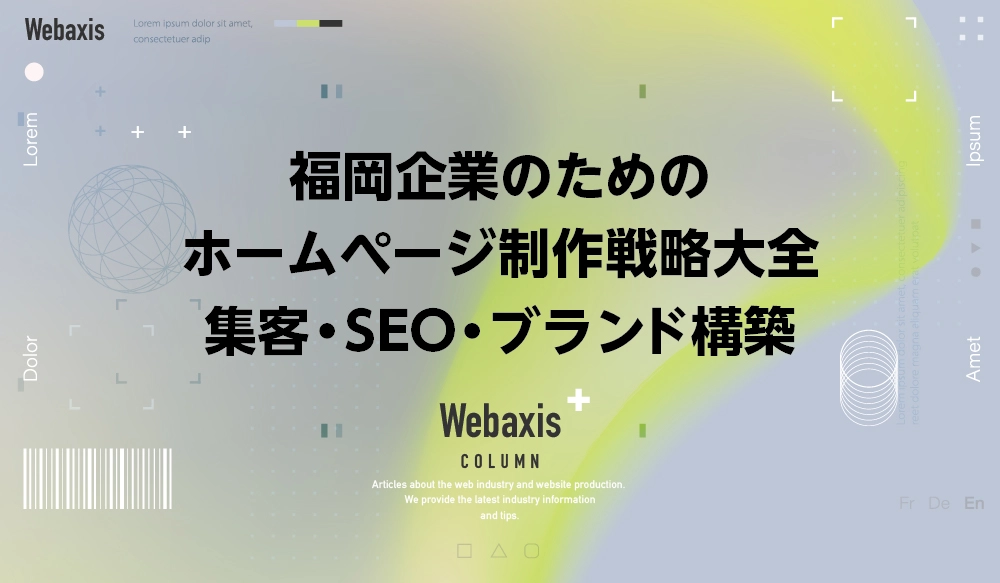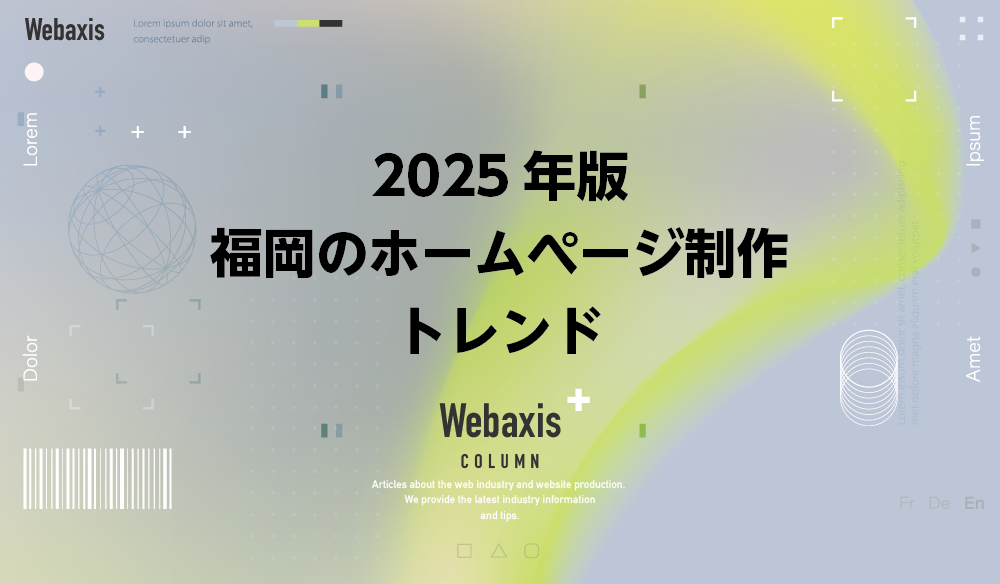SEOに強いホームページ制作の基本設計について
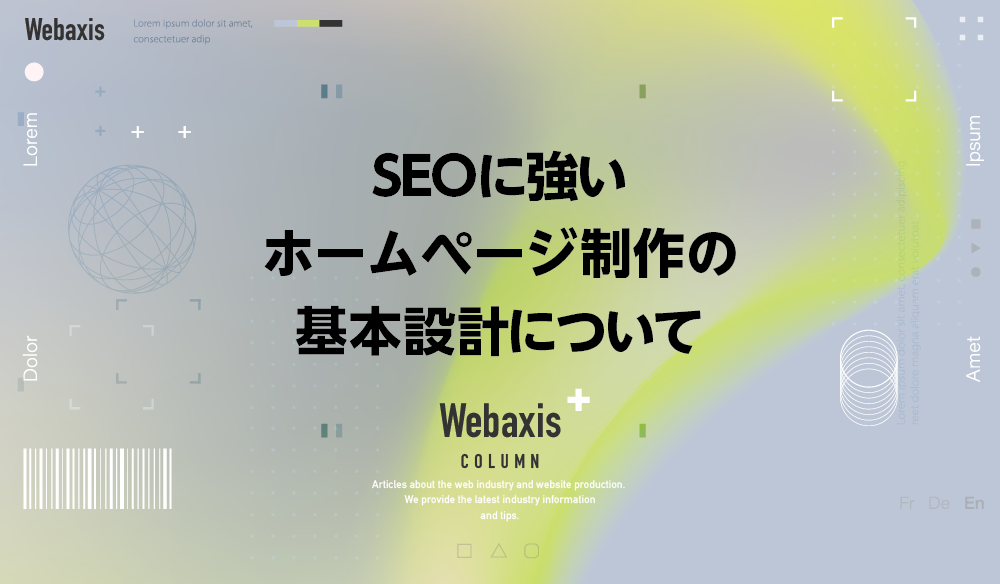
はじめに|なぜ今“SEOに強い”ホームページが必要なのか
2025年のGoogleコアアップデート以降、検索結果の評価基準は大きく変化しました。特に「ユーザーファースト」「文脈整合性」「E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)」の重要性が増し、ただキーワードを詰め込むだけでは上位表示は困難になっています。さらに、福岡の企業間競争も激化しており、地元市場での存在感を高めるためには、SEOを戦略的に組み込んだホームページ設計が不可欠です。本記事では、内部対策・外部対策・技術的SEOの三本柱を軸に、福岡企業が実務で活用できる具体的なSEO強化ポイントを体系的に解説します。
目次
SEOの基本構造を理解する
SEOの成功は「内部対策」「外部対策」「技術的SEO」の3つがバランスよく機能することで成り立ちます。内部だけを強化しても被リンクや技術面が弱ければ評価は頭打ちになり、逆も同様です。まずはこの3要素の全体像を理解し、自社サイトの課題がどこにあるのかを把握することから始めましょう。
SEOの3要素(内部対策・外部対策・技術的SEO)
- 内部対策:HTML構造、コンテンツ設計、内部リンクの最適化
- 外部対策:被リンク獲得、ブランド言及、SNSからの評価
- 技術的SEO:モバイル対応、表示速度、構造化データの実装
これらを同時並行で改善することで、Googleの評価は着実に向上します。
Googleが評価するコンテンツ品質とは
Googleは、コンテンツを評価する際に「量」よりも「質」を重視します。特に2025年のコアアップデート以降は、ユーザーの検索意図を正確に満たすかどうかと、その情報が信頼できる根拠に基づいているかが評価の中心になっています。
評価を高めるためのポイントは以下の通りです。
- 一次情報の提供 自社で得たデータ、事例、経験談など、他では得られない情報を盛り込む。
- 専門性の明示 執筆者の実績や所属、資格などを明記し、情報源の信頼性を高める。
- 文脈整合性 ページ全体の構成が検索意図に沿っており、不要な脱線がないこと。
- 網羅性 関連する質問や背景情報まで含め、ユーザーが追加検索せずに満足できる状態にする。
- 最新性 情報やデータが古くなっていないかを定期的に見直し、アップデートする。
実例
例えば、ある福岡市内の製造業企業がホームページ制作後にコンテンツを地域特化型に刷新したところ、公開3か月後の地域名+業種キーワードでの検索順位が15位から3位に上昇し、商談数が月平均4件から12件に増加しました。この成果の背景には、自社の製造プロセス写真や工場見学レポートなど、競合にはない一次情報の掲載がありました。
統計データ
Googleが公表した2024年の検索品質評価ガイドラインによると、検索上位10件のうち約82%が明確な著者情報と一次情報を含んでいるという結果があります(Google Search Central調べ)。これは単なるSEOテクニックではなく、ユーザーの信頼を獲得する情報設計こそが検索順位に直結することを示しています。
特に、福岡市場をターゲットにする場合は、全国的な情報に加えて地域特有のデータや事例を盛り込むことが、検索順位とユーザー評価の両面で効果的です。

キーワード戦略の設計方法
検索エンジンで上位を狙うための出発点は、正しいキーワード戦略の設計にあります。単に検索ボリュームが多い言葉を狙うのではなく、ターゲットの検索意図や購買プロセスに沿ったキーワードを選定することが重要です。特に2025年のGoogleコアアップデート以降は、検索文脈とユーザー満足度の一致が評価の中心になっており、「量より質」の戦略が必須になっています。Webaxisでは、福岡の地域特性を反映させたローカルSEOと、企業のブランドメッセージを損なわない自然なキーワード設計を組み合わせ、集客とブランド構築を同時に達成する手法を採用しています。
検索意図に基づくキーワード分類
キーワードは、ユーザーの目的に応じて以下の3タイプに分類されます。
- 情報探索型(Informational):例「ホームページ 制作 流れ」
- 比較検討型(Navigational/Consideration):例「福岡 ホームページ制作会社 比較」
- 購買直前型(Transactional):例「福岡 ホームページ制作 見積もり」
この分類により、ページごとに狙う役割を明確化し、無駄な競合を避けながら上位表示を目指します。
ロングテールとメインキーワードのバランス設計
ボリュームの大きいメインキーワードだけでなく、競合が少なく成約率の高いロングテールキーワードも戦略的に組み込みます。たとえば「福岡 ホームページ制作」だけでなく、「福岡 ホームページ制作 BtoB 事例」といった具体的な文脈を含むキーワードを活用します。
Webaxisの強み|ブランド一貫性を保つキーワード設計
多くの制作会社がSEO最適化とブランド表現を分断してしまう中、Webaxisは検索で見つけられる段階からブランド体験が始まることを重視します。見込み客が検索結果から受け取る第一印象をブランドメッセージと一致させ、クリック後の体験まで一貫性を保つキーワード設計を行います。
サイト構造と内部リンクの最適化
SEOに強いホームページを構築するうえで、サイト構造の設計は基礎中の基礎です。Googleはページ単体だけでなく、サイト全体の構造と情報のつながりを評価します。適切な階層設計と内部リンクの配置により、クローラビリティ(検索エンジンが情報を収集しやすくなる状態)が向上し、評価がページ全体に行き渡ります。さらに、ユーザー視点での回遊性を高めることで、直帰率低下や滞在時間向上にもつながります。
効果的なサイト階層の作り方
理想的な構造は、トップページから3クリック以内で主要ページにアクセスできる設計です。カテゴリやタグを用いた情報整理により、ユーザーが目的の情報にたどり着くまでの導線を短縮します。また、パンくずリストや明確な見出し構造(h1〜h3)を設けることで、検索エンジンがページの位置づけを正しく理解できます。
内部リンクの役割と設計ポイント
内部リンクは単なるナビゲーションではなく、ページ同士の関連性を検索エンジンに示す重要なシグナルです。関連する記事やサービスページ間を相互にリンクさせることで、SEO評価の流れ(リンクジュース)を効果的に分配します。リンクアンカーテキストには「こちら」ではなく、キーワードを含んだ自然な文章を使用します。
ブランド体験を意識した構造設計
近年は、SEOの最適化と同時に、ブランドとしてのメッセージやストーリーが自然に伝わる構造が求められます。例えば、サービスページから事例ページ、さらにお問い合わせページへと進む流れの中で、企業の価値や信頼感が段階的に伝わるよう設計することが重要です。実務では、こうした導線をUI/UXの一部として組み込むことで、検索評価とブランド体験を同時に高めることが可能になります。
モバイルファーストとページスピード最適化
モバイル端末からのアクセスが全体の7割以上を占める現在、モバイルファーストの設計はホームページ制作における必須条件です。Googleはすでに「モバイルファーストインデックス(MFI)」を採用しており、スマートフォンでの表示や操作性を基準に検索評価を行っています。そのため、PC版だけを基準にデザインやコンテンツを組む時代は終わりました。さらに、ページスピードの遅延は直帰率の上昇やコンバージョン率の低下を招くため、技術面の最適化も不可欠です。
モバイルUXの重要性
モバイルユーザーは、移動中や短時間で情報を得たいケースが多く、ファーストビューで必要な情報が得られない場合、すぐに離脱します。文字サイズ・タップ領域・行間・スクロール量など、操作性を考慮したUI設計が求められます。特にフォーム入力やCTA(Call To Action)の配置は、親指でスムーズに操作できる位置に設計すると効果的です。
ページスピード改善の実践ポイント
速度改善は、ユーザー体験とSEO評価の双方に直結します。以下の施策は効果的です。
- 画像のWebP形式への変換と遅延読み込み(Lazy Load)
- 不要なJavaScript・CSSの削減と軽量化
- キャッシュの活用とCDN(Content Delivery Network)の導入
- サーバー応答時間(TTFB)の短縮
特にコアウェブバイタル(Core Web Vitals)の「LCP」「FID」「CLS」は、Googleの評価基準に直結するため、定期的な計測と改善が必要です。
ブランド体験とモバイル設計の関係
モバイル設計は単に技術的な最適化だけではなく、ブランド体験の一部として機能します。例えば、スクロールに合わせて商品ストーリーや企業理念が自然に展開される演出は、UXとブランドイメージを同時に高めます。実務では、WebaxisのようにUI/UXデザインとパフォーマンス改善を一体化して設計することで、見た目の美しさと高速表示を両立させ、ユーザーに「また訪れたい」と感じてもらえるサイトを実現できます。

コンテンツ品質とGoogleの評価基準
Googleは近年、「検索結果に表示するコンテンツは、ユーザーにとって価値のある情報でなければならない」という姿勢をより鮮明にしています。2025年のGoogleコアアップデートでは、単なるキーワードの羅列や文字数稼ぎでは評価されず、ユーザー意図との整合性と情報の信頼性が評価軸の中心に据えられました。そのため、ホームページ制作時点からコンテンツ品質の基準を明確にし、制作と運用の両面で担保していく必要があります。
Googleが評価するコンテンツ品質とは
Googleの品質評価ガイドラインでは、以下の要素が高品質コンテンツの条件として挙げられています。
- **E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)**の明確な提示 → 専門知識や実務経験に裏付けられた情報提供
- 検索意図との完全一致 → 検索クエリに対して過不足なく、かつ深い回答を提供
- 一次情報の含有率 → 実際の事例・データ・現場の写真や動画などオリジナル情報の掲載
- 構造的で読みやすい情報設計 → 見出し・段落・箇条書きの適切な配置と内部リンク構造
特に、E-E-A-Tは「誰がその情報を発信しているのか」「なぜその発信元を信頼できるのか」が重視されるため、企業のプロフィールや著者情報の明示も有効です。
ブランド視点から見たコンテンツ設計
高品質なコンテンツはSEOのためだけではなく、ブランドイメージの醸成にも直結します。例えば、商品やサービスの説明において、機能だけでなく開発背景や企業の価値観をストーリーとして組み込むことで、訪問者との心理的距離を縮められます。
Webaxisでは、この「ブランドストーリーテリング」と「検索評価基準の両立」を得意としており、クライアント企業の経験や価値観をSEO設計に自然に反映させることで、競合との差別化を図っています。
実務での品質管理プロセス
コンテンツ品質を維持するには、制作後も継続的な点検と改善が必要です。定期的にアクセス解析やヒートマップを活用し、滞在時間や離脱率の変化を確認。検索順位やクリック率(CTR)の低下が見られるページは、最新情報の追加や構成の見直しを行います。こうしたサイクルを運用チーム全体で回すことで、サイト全体の品質を常に高い水準に保つことができます。
SEO内部施策の基本|構造化データと内部リンク戦略
SEO内部施策は、検索エンジンとユーザーの双方にとって情報を理解しやすくするための基盤作りです。2025年のGoogleコアアップデート後は、ページ単位の評価だけでなくサイト全体の文脈整合性が強く求められるようになりました。そのため、ホームページ制作段階からサイト構造・リンク設計・マークアップの最適化を行うことが、長期的な検索評価に直結します。
内部リンクとクラスター構造の設計
内部リンクは、検索エンジンに「ページ同士の関連性」を伝えるための重要な要素です。単純なリンク数の増加ではなく、関連度の高いページ同士を体系的に結び、トピッククラスターを形成することで、サイト全体のテーマ性が明確になります。
例えば「福岡 ホームページ制作」に関する情報を集約する親ページを設け、その下に制作事例、SEO対策、SNS連携といった関連コンテンツを配置すると、Googleはサイト全体を専門的な情報源として評価します。
Webaxisでは、このトピッククラスター設計をSEO戦略の起点としており、クライアントのビジネス領域に合わせた内部リンクマップを事前に構築します。
構造化データ(Schema.org)による検索結果最適化
構造化データとは、ページ内の情報を検索エンジンが理解できる形式でマークアップする仕組みです。これを適切に設定することで、検索結果にリッチリザルト(星評価、FAQ、イベント情報など)を表示させ、CTRを向上させることができます。
代表的な構造化データの例には以下があります。
- Organization:会社概要やロゴ、連絡先情報
- BreadcrumbList:パンくずリスト構造
- FAQPage:よくある質問
- Product:製品やサービスの詳細情報
特にFAQPageやBreadcrumbListは、サイトの回遊性と検索結果での視認性を同時に高められるため、制作段階での実装が推奨されます。Webaxisでは、Google Search Consoleのリッチリザルトレポートを活用し、構造化データのエラーや警告を定期的にチェックしながら改善を行っています。
SEO外部施策とブランドの信頼性向上
SEO外部施策は、自社サイト外での評価を高める取り組みです。検索エンジンは被リンクやブランド言及を、コンテンツの信頼性・権威性を示すシグナルとして重視します。2025年以降はリンクの「質」と「文脈の一致」が評価軸の中心となり、単にリンク数を増やす施策はほぼ効果を失っています。外部施策は、ブランド価値の向上と自然な評価獲得を目的に計画的に行うことが重要です。
被リンク獲得戦略とブランド言及の増やし方
自然な被リンクを得るためには、他サイトが参照したくなる独自コンテンツの発信が不可欠です。統計データ、業界調査、成功事例、インフォグラフィックスなど、引用価値の高いコンテンツを制作しましょう。また、地元メディアや業界団体との関係構築、セミナー・イベントの開催も有効です。
例えば、Webaxisでは制作実績ページや調査レポートをSEOと連動させ、地元企業やメディアに取り上げられる機会を増やす設計を行っています。これにより、単なるリンク獲得ではなく「福岡の〇〇分野ならこの会社」というブランド想起を強化できます。
SNSとホームページの相互連携による認知拡大
SNSは直接的なSEO効果は限定的ですが、コンテンツ拡散とブランド認知の加速には欠かせません。特にX(旧Twitter)、Instagram、LinkedInなどは、ターゲット層や業種によって有効なチャネルが異なります。
ホームページとSNSを連動させる際は、以下のポイントを押さえましょう。
- 記事や事例ページをSNS用に要約して発信
- ハッシュタグ戦略で発見性を高める
- SNS投稿からホームページへの明確な動線を設計
Webaxisでは、制作したホームページを中心にSNS運用計画も設計し、更新頻度やクリエイティブの方向性を統一しています。これにより、オンライン上のブランド体験が分断されず、一貫した認知拡大が可能になります。

セキュリティとサイトパフォーマンス|信頼性とUXの裏側
ホームページのセキュリティとパフォーマンスは、ユーザー体験だけでなく検索順位にも直結します。表示速度が遅かったり、セキュリティ警告が出るサイトは、ユーザー離脱率が高まり、コンバージョンにも悪影響を及ぼします。特に2025年のGoogleコアアップデートでは、Core Web VitalsやHTTPS化などの基本項目が、より明確に評価指標として組み込まれています。信頼されるWebサイトの運用には、これらの要素を継続的に最適化する体制が欠かせません。
SSL/TLS対応とHTTPS化の重要性
SSL/TLSを導入しHTTPS化することは、もはや必須条件です。通信が暗号化されることで、ユーザーの個人情報やフォーム送信データを安全に保護でき、ブラウザ警告の表示も防げます。また、GoogleはHTTPSをランキングシグナルとして明言しており、SEO上の優位性も得られます。
福岡の企業サイトでは、古い証明書のまま更新が止まっているケースも散見されます。Webaxisでは、SSL更新の自動化や期限管理を含めた運用設計を行い、セキュリティリスクを最小化しています。
Core Web Vitals最適化の実践ポイント
Core Web Vitals(LCP・FID・CLS)は、ページの読み込み速度、インタラクションの応答性、表示の安定性を測る指標です。これらの改善は、UXの向上とSEO評価の両面で効果を発揮します。具体的な施策としては以下が挙げられます。
- 画像のWebP形式への変換と遅延読み込み
- 不要なJavaScript・CSSの削除と圧縮
- サーバー応答速度(TTFB)の短縮
- CDNの導入による配信最適化
Webaxisでは制作段階からPageSpeed InsightsやLighthouseで計測し、公開前に90点以上を目標値とする品質基準を設けています。これにより、ユーザーが快適に利用できるだけでなく、Googleからの評価も得やすい状態でリリースできます。
公開後の分析と改善サイクル|PDCAで成長するサイト運用
ホームページは公開がゴールではなく、スタートです。特にリニューアル直後は、アクセスやコンバージョンの動きが大きく変化するため、適切な分析と改善サイクル(PDCA)が成否を左右します。2025年のGoogleコアアップデート以降は、ユーザー行動データの分析精度と改善スピードが評価にも直結し、継続的な運用体制が不可欠になっています。
GA4とヒートマップツールの活用方法(Clarity・Hotjar等)
GA4ではページごとのコンバージョン率やユーザー属性、流入経路を把握できますが、それだけでは「なぜ離脱したのか」という理由までは掴めません。そこで活躍するのがClarityやHotjarといったヒートマップ・セッション録画ツールです。
- ヒートマップ分析:ユーザーがどこまでスクロールしているか、どこをクリックしているかを可視化
- セッション録画:実際のユーザー行動を動画として確認でき、フォーム離脱や操作ミスの原因を特定
- ファネル分析:各ステップでの離脱ポイントを数値化し、改善の優先度を判断
Webaxisでは、GA4とヒートマップデータを掛け合わせて「数値+行動」の両面から改善提案を行い、実装まで一貫してサポートしています。
改善施策の優先順位付けと実行
改善点を洗い出したら、すぐに着手するのではなく、インパクトと実装コストのバランスを見て優先順位を決めます。たとえば、ボタンの色や位置の変更など即効性が高いUI改善は短期で実施し、サイト構造の見直しやコンテンツの大幅追加など時間のかかる施策は中長期計画に組み込みます。
また、改善の効果測定は1回で終わらず、Plan → Do → See → Improve のサイクルを回し続けることが重要です。Webaxisではこのプロセスを運用に組み込み、数値的根拠に基づく継続改善を支援しています。
制作パートナーの選び方|福岡で信頼できる制作会社の基準
ホームページ制作の成功は、パートナー選びに大きく左右されます。特に福岡の市場では制作会社の数が多く、料金・得意分野・サポート体制が千差万別です。2025年のGoogleコアアップデート以降は、制作だけでなく運用・改善まで見据えた長期的なパートナーシップが重要になっています。
制作会社選びのチェックリスト
制作会社を選定する際には、以下の観点を総合的に確認しましょう。
- 実績の透明性:公式サイトやポートフォリオで公開している事例の分野や成果を確認
- 戦略提案力:単なるデザイン提案ではなく、SEO・SNS・広告を含めた集客戦略が提示されるか
- 運用サポート体制:公開後の改善提案やデータ分析まで対応可能か
- コミュニケーションの質:担当者のレスポンス、要望の汲み取り力、説明のわかりやすさ
- 契約条件の明確さ:著作権や運用権限、解約条件が契約書に明記されているか
Webaxisでは、これらすべての項目を網羅した上で、福岡企業の業種特性に合わせた“オーダーメイド型”の提案を行っています。
見積もり比較と契約時の注意点
見積もりは金額だけで判断せず、内訳の明細化が重要です。同じ金額でも、含まれる作業範囲(デザイン、コーディング、SEO設定、運用サポートなど)が異なる場合があります。また契約時には以下を必ず確認しましょう。
- 納品物の権利関係:ソースコードやデザインデータの所有権が誰に帰属するか
- 追加費用の発生条件:仕様変更やコンテンツ追加時の費用計算方法
- サポート期間と内容:公開後の更新・トラブル対応の有無と範囲
こうした点を事前にクリアにすることで、制作後のトラブルを防ぎ、安心して長期運用に専念できます。
まとめ|リニューアルで成果を出すために
ホームページのリニューアルは単なる見た目の刷新ではなく、企業の成長戦略に直結する重要な投資です。本記事で解説した10のポイントは、企画から運用までの各段階で軸となる考え方を示しています。
本記事の重要ポイント総括
- 目的とKPIの明確化でリニューアルの方向性を定める
- ターゲット再定義により、既存顧客と新規層の双方に訴求
- コンテンツ刷新は検索意図とE-E-A-Tを基盤に設計
- UI/UX改善でブランド体験とコンバージョンを強化
- SEO内部・外部施策を総合的に見直す
- パフォーマンス・セキュリティ強化で信頼性を高める
- 継続改善の仕組み化で成果を伸ばし続ける
- 適切な制作パートナー選びが成功の成否を分ける
こうした全体最適の視点を持つことで、単発的なリニューアルではなく、成果が積み上がる長期運用が可能になります。
2025年以降のホームページ運用の方向性
Googleコアアップデート2025以降、検索評価は「ユーザーファースト」と「文脈整合性」へと一層シフトしています。また、AI活用・動画コンテンツ・インタラクティブUIなど、運用の選択肢も拡大中です。リニューアル後は、ユーザー行動データを活用した改善サイクルと、多チャネルでのブランド体験統一が成果の持続に直結します。
Webaxisでは、福岡企業の市場特性や業種ごとの課題に沿った戦略設計から運用改善までワンストップで伴走しています。もし貴社のホームページが「デザインは変わったけれど成果が伸びない」という状況であれば、今が戦略的リニューアルのタイミングです。
本記事で解説した内容は、全体戦略の一部に過ぎません。福岡の企業が成果を出すための体系的な取り組みは『福岡企業のためのホームページ制作戦略大全|集客・SEO・ブランド構築』で詳しく紹介しています。