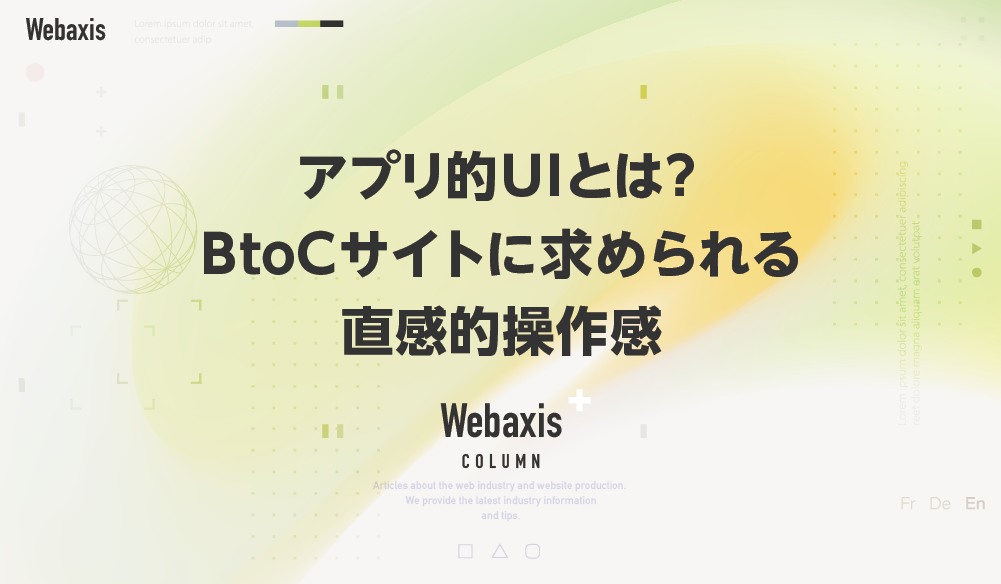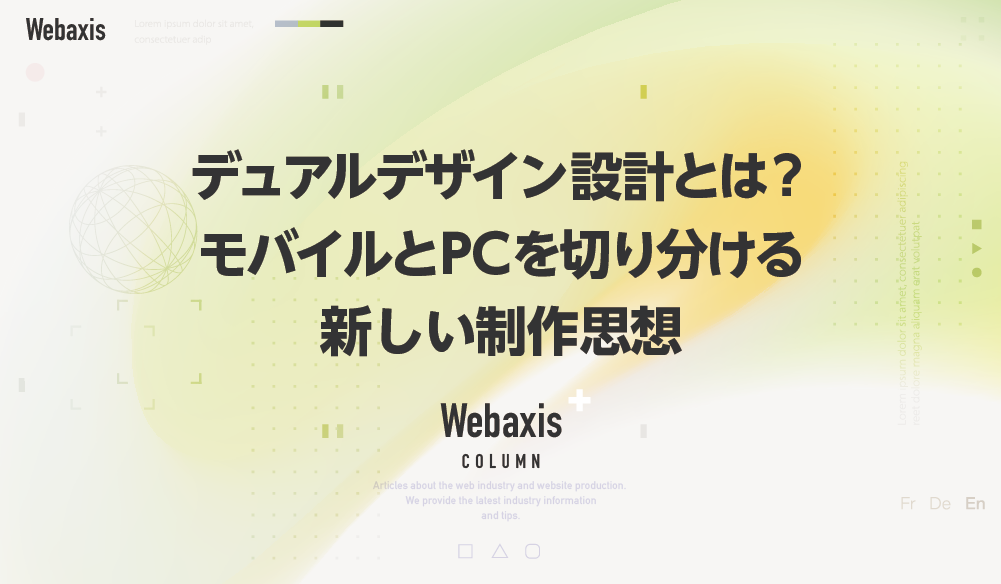スマホファーストデザインとブランディングの両立方法
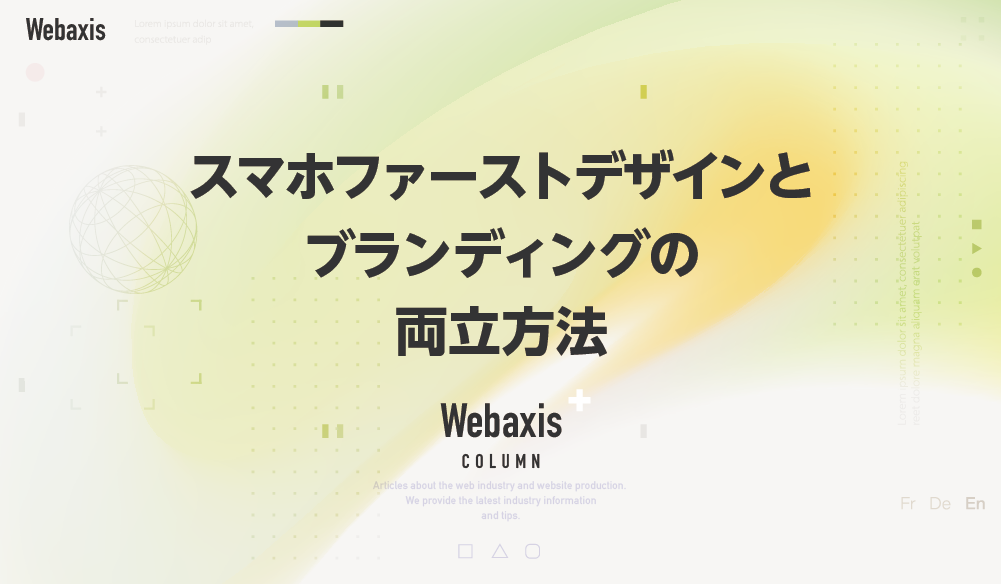
スマホファーストが当たり前となった今、Webサイトは「見やすさ」「使いやすさ」を最優先とするUI設計が求められています。しかしその一方で、企業にとって欠かせないのが「ブランドらしさの表現」です。
特にBtoCサイトでは、Google検索や Instagram・TikTokのハッシュタグ検索 から初めて訪れたユーザーが数秒で「このサイトに信頼できるか」を判断します。そのためUIの簡素化だけを追求すると世界観が伝わらず、逆にブランド表現を優先しすぎるとUXを損ねる可能性もあります。
本記事では、この矛盾をどう乗り越え、デュアルデザイン設計の視点から両立を実現するかを解説します。
目次
スマホファーストとブランドデザインの矛盾
スマホファーストの基本は「シンプルさ」です。無駄を削ぎ落としたUIは操作性を高めますが、その反面「ブランドの世界観が表現しきれない」というジレンマを生みます。
特にBtoCサイトでは、飲食なら「おいしそうな体験」、美容なら「美しさや信頼感」、ECなら「購買意欲を刺激する魅力」、旅行なら「ワクワク感や安心感」を伝えることがブランドの役割です。
ここではまず、スマホファーストとブランドデザインが対立する2つの典型的なリスクを整理します。
UIの簡素化がブランド要素を削ぎ落とすリスク(約330字)
スマホファーストの設計思想では、操作性を高めるために余白やアイコンの最適化を重視します。しかし、シンプルさを追求しすぎると、ブランドカラーやフォント、ビジュアル表現といった要素が削ぎ落とされてしまい「どの企業のサイトかわからない」という無個性なデザインに陥りやすくなります。
例えば飲食サイトで写真の強調を避けすぎると「食欲をそそる体験」が薄れ、美容サイトでフォントやカラーを標準化しすぎると「高級感」が伝わりません。ブランド要素を適度に残しつつ簡潔にまとめることが、成果に直結するバランス設計の第一歩です。
ブランド重視がUXを阻害するリスク
逆に、ブランド表現を優先しすぎるとUXを阻害します。たとえば独自性を出そうと複雑なアニメーションや装飾を多用した場合、ページ速度(LCP)が低下し、ユーザーは読み込みの遅さにストレスを感じます。
また、凝ったデザインでメニューやボタンがわかりにくくなると、コンバージョン導線を見失うリスクもあります。特に SNS検索から訪問する初回ユーザー は「快適かどうか」を数秒で判断するため、ブランド表現が強すぎて操作しづらいサイトは即離脱につながります。
つまり「世界観を伝える」ことと「行動を促す」ことを両立させる仕組みが欠かせないのです。
UIの簡潔さとブランド表現の両立
スマホファーストの設計においては、UIをシンプルに保つことが基本です。しかし、そのままではブランドの独自性や世界観が失われてしまうリスクがあります。
重要なのは「必要最小限の要素でブランドを伝える」ことです。
例えば飲食なら「色彩や写真で食欲を刺激する」、美容なら「フォントや余白で高級感を演出する」、ECなら「商品写真の質で信頼性を示す」といったように、UIを簡素化しながらもブランド要素を巧みに織り込む設計が求められます。ここでは、UIとブランド表現を両立させる具体的なデザインの考え方を整理します。
ミニマルなUIに世界観を織り込むデザイン手法
UIを極力シンプルにした上でブランドを表現するには「引き算」と「残す要素の選択」がカギとなります。例えば美容サロンのサイトであれば、余白を活かしたミニマルなレイアウトにブランドカラーを一貫して用いることで、簡潔ながらも世界観を伝えられます。
飲食サイトであれば、文字要素を最小限に抑えつつ、料理写真に力を入れることでブランドの強みを表現可能です。つまり「装飾」ではなく「体験の本質に関わる要素」を残すことが、スマホファーストとブランディングの両立につながります。
カラー・タイポグラフィ・ビジュアルの役割
ブランドを最も強く印象付けるのは「色・フォント・ビジュアル」です。例えば高級ホテルのサイトであれば落ち着いた色合いと明朝体フォント、美容サロンであれば洗練されたサンセリフ体と明るいカラー、といった具合に、UIが簡潔であってもブランドのイメージを強く訴求できます。
ここで重要なのは「一貫性」です。SNS検索から訪問したユーザーがブランドのInstagram投稿を見てから公式サイトに来た際に、色やビジュアルのトーンが一致していれば「期待通りの体験だ」と感じ、ブランドへの信頼感が高まります。
事例に見る成功パターン
スマホファーストとブランディングの両立は、理論だけでなく「どのように実装されているか」を確認することで理解が深まります。
ここでは、実際に公開されている有名ブランドの公式サイトを参考に、BtoCサイトにおける成功パターンを整理します。飲食・美容・EC・旅行の各業界で「UIの簡潔さ」と「ブランド表現」をどのように融合させているのかを見ていきましょう。
いずれもGoogle検索や Instagram/TikTokのハッシュタグ検索 を経由して訪れるユーザーを想定し、快適な体験と世界観の一致を実現しています。
飲食業界|スターバックス
スターバックス公式サイトは、モバイル画面で写真主体のデザインを採用しています。メニュー写真や季節限定商品が大きく表示され、余白を活かしたシンプルなUIの中にブランドらしい世界観を保っています。また、注文や店舗検索への導線がフローティングCTAで常に表示されており、スマホでの操作性とブランド体験を両立している好例です。
出典:スターバックス公式サイト
美容業界|資生堂
資生堂のグローバルサイトは、ブランドカラーを基調にタイポグラフィを統一しており、スマホ表示でも「高級感」と「世界観」が崩れません。商品紹介ページは写真とテキストをミニマルに配置し、購入ボタンはわかりやすく親指ゾーンに設置。これにより、ブランドの価値を損なわずUXを維持するバランスを実現しています。
出典:資生堂公式サイト
EC業界|ユニクロ
ユニクロの公式ECサイトは、スマホでも商品一覧がカード型レイアウトで整然と並び、ユーザーが直感的に比較・購入できます。シンプルで高速なUIを維持しながらも、ブランドらしい写真演出やキャンペーンビジュアルで「買いやすさ」と「ブランド体験」を同時に提供しています。
旅行業界|Airbnb
Airbnbは「非日常体験を届ける写真」と「直感的な検索UI」を両立させた代表例です。モバイルサイトでは大きな写真が印象を与えると同時に、検索バーが常に上部に表示され、スムーズに宿泊プランを探せます。ビジュアルによる世界観と、実用的なUXを兼ね備えたグローバルな成功パターンです。
👉 出典:Airbnb公式サイト
業界別「UI × ブランド表現」整理表
| 業界 | 参考ブランド | UIの工夫 | ブランド表現の工夫 |
|---|---|---|---|
| 飲食 | スターバックス | 写真主体+フローティングCTA | 季節感・世界観を余白で表現 |
| 美容 | 資生堂 | ミニマルUI+親指ゾーン導線 | ブランドカラーとタイポグラフィで高級感 |
| EC | ユニクロ | カード型レイアウトで比較容易 | 写真演出でシンプルにブランド維持 |
| 旅行 | Airbnb | 写真訴求+固定検索バー | 非日常感のあるビジュアルとUX融合 |
デュアルデザイン設計が果たす役割
スマホファーストとブランドデザインの両立は、多くの企業が直面する課題です。
シンプルにすれば世界観が失われ、ブランドを優先すればUXが犠牲になる――この矛盾を解消する鍵となるのが デュアルデザイン設計 です。Webaxisが提唱するこの設計思想は、PCとモバイルを同一レイアウトに押し込むのではなく、それぞれのデバイスの特性とユーザー行動に最適化して設計する方法です。
結果として、ブランド表現に必要な要素を確保しつつ、スマホでの快適さも失わない「二重の最適化」を実現できます。
PCとモバイルを分けることで得られる表現自由度
従来のレスポンシブ設計では、PC用のデザインを縮小してスマホに適用するケースが多く、モバイル画面では情報が詰まりすぎたり、逆にブランド表現が削られてしまう課題がありました。
デュアルデザイン設計では、PC版はビジュアルを大胆に使いブランドストーリーを語り、モバイル版はシンプルなUIで直感的な操作を実現する、といった役割分担が可能です。これにより「どちらかを犠牲にする」のではなく、両方で最適な体験を提供できます。
ユーザー行動に合わせたブランド体験設計
ユーザーはPCとスマホで異なる目的や行動を取ります。例えばPCでは「じっくり比較・検討」、スマホでは「その場で予約・購入」といった行動が多いのが実態です。
デュアルデザイン設計では、この行動差を前提に「モバイルは決断を促すUI」「PCはブランドの背景や信頼感を伝えるデザイン」と役割を分けることで、両者を補完し合う仕組みを構築します。
特にBtoCサイトでは、SNS検索から流入したスマホユーザーが即決しやすいUIを持ちつつ、PCで深いブランド体験を提供する流れが成果に直結します。
まとめ|ユーザー体験がブランドを強化する
スマホファーストとブランディングの両立は、一見すると矛盾するテーマに見えます。しかし実際には、両者を補完し合う関係にあります。
シンプルなUIが快適な操作を提供し、ブランド表現が「世界観」や「信頼感」を与える――この二つが合わさることで、初めてユーザーに選ばれるサイトとなります。
特にBtoCサイトでは、Google検索や Instagram・TikTokのハッシュタグ検索 から訪問するユーザーが多く、第一印象で「快適かつブランドらしい」と思わせられるかどうかが成果を分けます。
スマホファーストは「制限」ではなく「進化」
スマホファーストは「ブランド表現を削るための制約」ではなく、「ユーザー行動に最適化するための進化」です。
限られた画面サイズだからこそ、余計な装飾を削ぎ落とし、本当に伝えたいメッセージを際立たせられます。
飲食では「写真」、美容では「色とタイポグラフィ」、ECでは「購入導線」、旅行では「非日常を伝えるビジュアル」など、業界ごとに重視すべき要素は異なりますが、いずれも「本質を残す」ことがブランド強化につながります。
ブランドとUXを両立させるにはご相談ください
最適なバランスは業界・商材・ユーザー層によって異なります。UIを極端に簡略化するとブランドが伝わらず、逆にブランド表現を優先しすぎると操作性を損なうリスクがあります。
こうした矛盾を解消するには、PCとモバイルを切り分けた デュアルデザイン設計 が効果的です。私たちWebaxisでは、検索行動からSNS経由までを踏まえた設計で「成果とブランド」を両立するホームページ制作を提案しています。自社の課題に合った改善策を知りたい方は、ぜひご相談ください。
BtoCサイトにおけるモバイルファーストやデュアルデザイン設計の考え方は、単体の手法だけでは成果につながりません。
検索から始まるユーザー体験を一貫して設計するためには、全体像を理解したうえで、自社サイトに最適な施策を選択することが大切です。
▶ 関連記事: