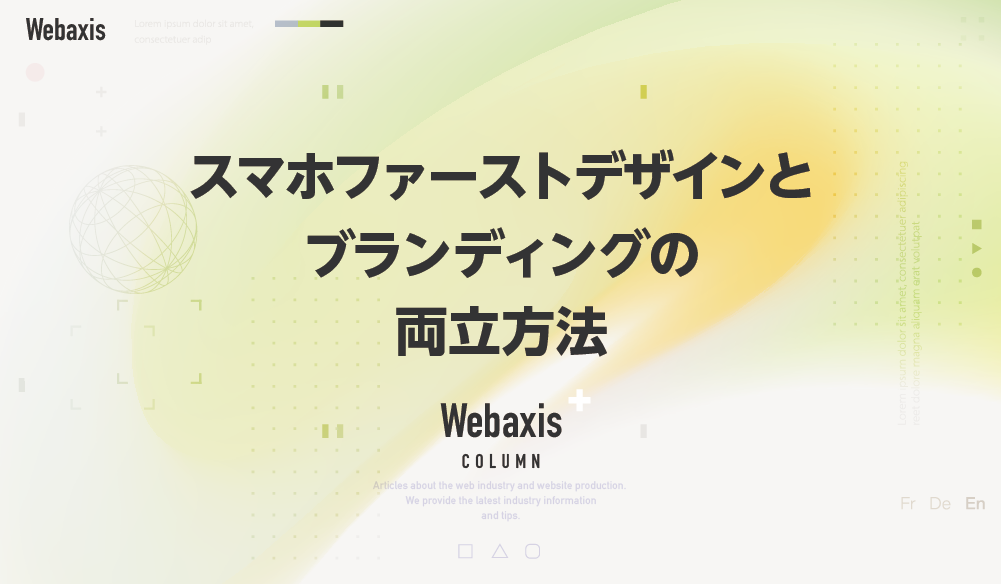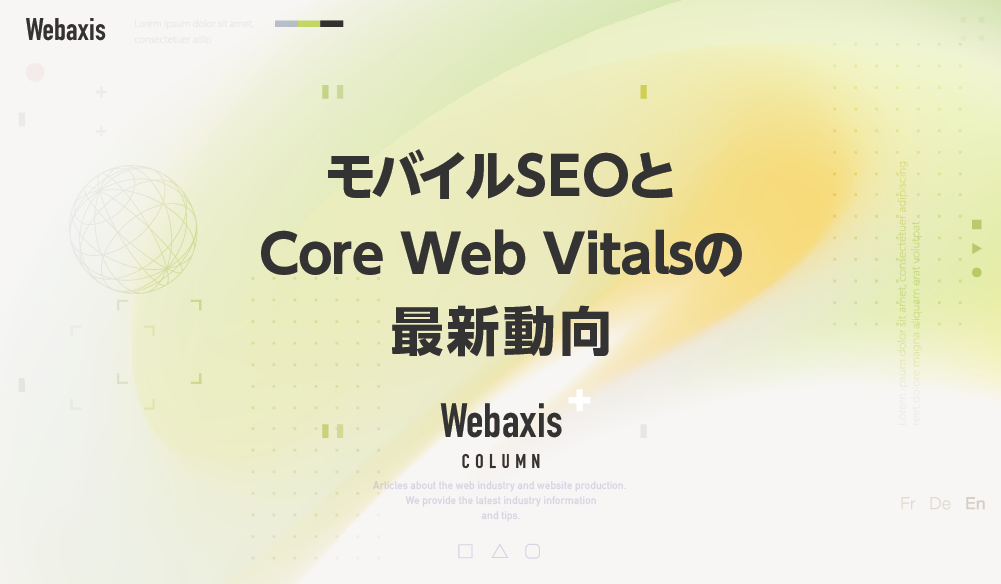デュアルデザイン設計とは?モバイルとPCを切り分ける新しい制作思想
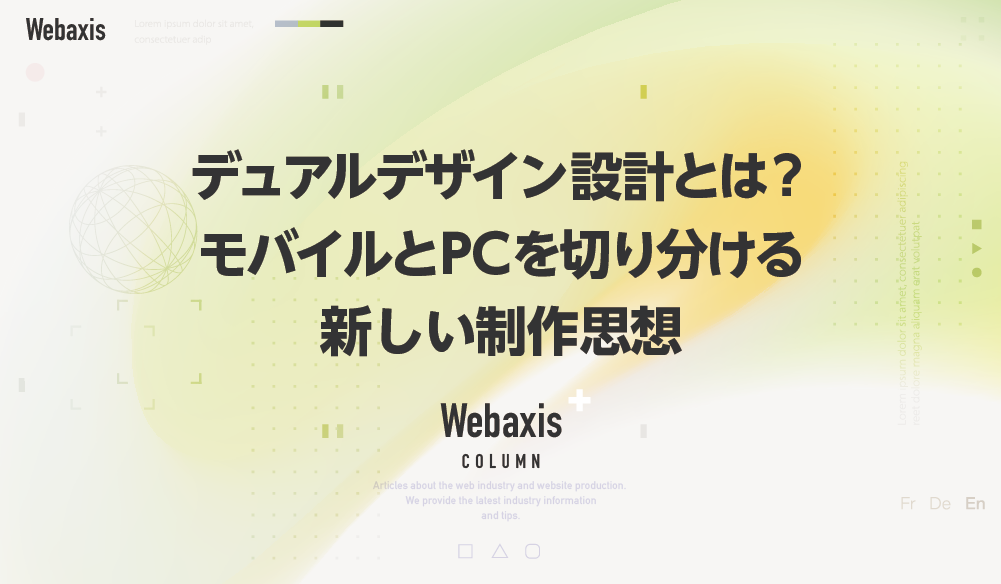
レスポンシブ対応をしているのに「スマホで成果が出ない」と感じたことはありませんか?
その理由は、多くのサイトが「PCデザインをそのまま縮小」しているだけだからです。
本来、ユーザーがスマホで求めるのは「見える」ことではなく「行動しやすい」こと。飲食予約やEC購入、美容サロンの空き確認、旅行プランの検索など、意思決定の多くはスマホで行われます。そこで必要となるのが Webaxis独自の制作思想「デュアルデザイン設計」 です。PCとモバイルを同じものとして扱うのではなく、それぞれの利用文脈や役割に合わせて設計を切り分けることで、成果につながるBtoCホームページを構築できます。
目次
デュアルデザイン設計が生まれた背景
かつてはPCがインターネット利用の中心でした。そのためWebサイトの多くは「大きな画面での情報整理」を前提に作られてきました。ところがスマホが普及し、検索や比較、購入・予約といった行動が日常的にスマホで完結するようになると、従来の設計では成果が出にくいという課題が浮き彫りになったのです。
レスポンシブデザイン自体は一定の役割を果たしますが、操作性や導線の最適化までは担保できません。そこで生まれたのが「モバイルとPCを切り分け、それぞれに最適化する」という新しいアプローチ、デュアルデザイン設計です。
PC主導の時代からの転換
PC利用が中心だった時代は、横幅を活かした豊富な情報量、複雑なレイアウトが主流でした。しかしスマホでは、縦スクロールと親指操作が基本のため、同じ設計をそのまま縮小すると体験が破綻します。例えば「横に並べて見やすい表」が、スマホでは横スクロール必須の不便な表になってしまうのです。こうした限界を解消するために、デュアルデザイン設計では PC=検討・比較の場、モバイル=意思決定の場 と役割を分け、それぞれに最適な体験を設計することを重視しています。
スマホ中心時代における課題
スマホの普及により、ユーザーは「検索→比較→行動」までを数分以内に完了させるようになりました。飲食店予約なら数分、EC購入なら数十秒。このスピード感に対応できないサイトは、使いづらいと判断され、即座に競合に流れてしまいます。
レスポンシブ対応だけでは「行動スピード」への最適化が不十分であり、結果としてCVRの低下を招きます。デュアルデザイン設計は、この課題を解決するために誕生した思想であり、スマホユーザーが迷わず行動できる「意思決定設計」を前提としています。
PC縮小版レスポンシブとの決定的な違い
レスポンシブデザインは、1つのレイアウトを画面幅に応じて自動調整する仕組みとして広く普及しています。しかし実際のBtoCサイトでは「PC版をそのまま縮小」しただけのケースが多く、ユーザー体験を大きく損なっているのが現状です。ボタンが小さく押しにくい、情報が縦に延々と並ぶ、重要な導線が下層に埋もれる――こうした課題は成果を直撃します。
デュアルデザイン設計は、この「縮小レスポンシブの限界」を乗り越えるために生まれました。PCとモバイルを同一に扱うのではなく、それぞれを独立した体験として最適化することが、成果に直結する決定的な違いなのです。
縮小レスポンシブの典型的な課題
PC縮小版レスポンシブのサイトでは、以下のような課題が目立ちます。
- CTA(予約・購入ボタン)が小さすぎてタップしづらい
- フォントサイズが最適化されず、読みづらい文章が多い
- PC前提の横並び構造が縦長に変換され、情報が分かりにくい
- スクロール量が増え、ユーザーが目的に到達する前に離脱する
これらは「見えるけれど使いにくい」サイトを生み出し、CVR低下の要因となります。レスポンシブという技術そのものに問題はありませんが、設計思想がPC基準のままでは成果を出せないのです。
デュアルデザイン設計が解決するポイント
デュアルデザイン設計は、こうした課題を「スマホ専用の意思決定設計」で解決します。具体的には、ファーストビューに必ず行動導線を置き、親指ゾーンを意識したナビゲーションを導入。さらにPCとモバイルで表示順やコンテンツ構造を切り分けることで、ユーザーが求める情報に最短で到達できるように設計します。
たとえばECサイトなら、PCでは「商品比較とレビュー重視」、モバイルでは「購入ボタンの固定表示」を優先。こうして両デバイスの役割を前提に最適化することで、従来のレスポンシブでは到達できなかった成果を引き出せるのです。
PCとモバイル、それぞれの役割と体験設計
デュアルデザイン設計の核心は「PCとモバイルを同じ土俵で考えない」ことにあります。ユーザーはPCとモバイルを異なる場面で使い分けており、それぞれの役割に応じた体験を設計しなければ成果は得られません。PCはじっくり比較・検討する場であり、情報量や信頼性の担保が重視されます。
一方、モバイルは「今すぐ予約」「すぐに購入」といった意思決定が行われる場です。この違いを前提に導線やUIを変えることで、ユーザー体験は飛躍的に改善されます。以下では、PCとモバイルの役割の違いと、それに基づく体験設計の具体的な考え方を整理します。
PCは「検討と比較」の場
PCは画面が広いため、複数の情報を横並びに比較できるのが大きな強みです。BtoCサイトであれば、商品の詳細スペック比較や料金プランの違い、複数店舗のレビュー確認といった行動に向いています。
そのためPCサイトの設計では「表やグラフでの情報整理」「長文コンテンツでの信頼性担保」が有効です。ユーザーは腰を据えて情報収集するため、多少スクロールが長くても問題にはなりにくいのが特徴です。
つまりPCは「納得感を高める体験設計」を担うデバイスだと位置づけられます。
モバイルは「意思決定」の場
モバイルでは、ユーザーが情報を長時間かけて比較するよりも、直感的に「選ぶ」「予約する」行動を取る傾向が強く表れます。したがってスマホ設計では「最短で意思決定に到達できるUI」が鍵となります。
代表的な違いを整理すると以下の通りです。
| デバイス | 主な役割 | 設計の重点 |
|---|---|---|
| PC | 検討・比較 | 情報量、信頼性、比較機能 |
| モバイル | 意思決定 | 短い導線、即行動できるUI、迷わせない設計 |
飲食店であれば「空席確認と即予約」、ECなら「購入ボタンの常時表示」、美容なら「指名予約の即時入力」、旅行なら「料金とレビューをワンタップで確認」など、いかに素早く行動に結びつけるかが設計の肝になります。
アプリ的UIを取り入れたモバイル最適化
スマホユーザーが求めるのは「直感的に操作できる体験」です。ところが、従来のWebサイトはPC基準のデザインをそのまま流用しているため、操作性に違和感を覚えるケースが少なくありません。そこで注目されるのが「アプリ的UI」の導入です。アプリのように、迷わず操作できるインターフェースをWebサイトに取り入れることで、ユーザーはスムーズに行動できます。
特にBtoCサイトでは、予約・購入・問い合わせといった行動が数秒で判断されるため、この操作感の差がCVRに直結します。以下では、代表的なアプリ的UIの要素と、導入のポイントを整理します。
フローティングCTAとカード型レイアウト
スマホで重要なのは「常に行動できる状態を保つこと」です。フローティングCTA(画面下に常時表示されるボタン)は、その典型的な手法です。飲食店サイトなら「予約する」、ECサイトなら「カートに追加」といった行動をワンタップで行えます。
さらにカード型レイアウトを組み合わせると、商品やメニューを一覧で見やすく整理でき、タップもしやすくなります。これにより「探す」ストレスを減らし、自然な流れで行動に誘導できます。
ボトムナビゲーションと親指ゾーン
スマホ操作の多くは「親指」で行われます。そのためUIは親指の可動範囲、いわゆる「親指ゾーン」に配置することが重要です。特にBtoCサイトでは、ナビゲーションが画面上部に固定されていると、ユーザーは操作しにくく感じます。そこで効果的なのが ボトムナビゲーション です。
代表的な改善ポイントは以下の通りです。
- 主要なメニューを画面下に配置し、片手操作でアクセス可能にする
- アイコンと文字を組み合わせ、直感的に理解できるUIにする
- 「予約」「購入」「問い合わせ」など成果に直結する項目を優先配置する
このような工夫により、ユーザーは片手でスムーズに操作でき、ストレスなく行動に移せるようになります。
「検索から始まるブランド体験」との関係性
Webaxisが重視しているのは、単なるサイト制作ではなく「検索から始まるブランド体験」の設計です。ここでいう検索はGoogleなどの検索エンジンだけでなく、InstagramやTikTok、X(旧Twitter)などのSNSにおけるハッシュタグ検索やトレンド検索も含まれます。
実際にユーザーがブランドを最初に知るきっかけは「福岡 美容院 予約」といったGoogle検索だけでなく、「#博多カフェ」「#福岡旅行」といったSNS検索経由であることも増えています。つまり検索からの入口設計は、SEOとSNSを分断せず、連続的な体験としてつなぐことが、ブランド価値とCVRを高めるカギとなるのです。
検索結果から行動までを一貫設計する
ユーザーは「検索した瞬間に欲しい情報が得られるか」でブランドの第一印象を判断します。Google検索ならファーストビューに予約や購入導線、SNS検索なら投稿に直結する公式ページやリンクが用意されていることが必須です。
デュアルデザイン設計では、SEOでの検索意図分析とSNS検索行動の導線設計を組み合わせ、どの入口から来ても「行動につながる体験」を一貫して支援します。
例えば「飲食店×#即予約」「旅行×#格安プラン」など、検索行動をそのまま意思決定につなげられるのです。
ブランド価値を高める体験設計
検索から始まる体験をブランド価値につなげるには、「わかりやすさ」「安心感」「一貫性」の3要素が重要です。
- わかりやすさ:検索意図に応える情報をファーストビューで提示する
- 安心感:口コミ・実績・レビューをスマホで見やすく配置する
- 一貫性:検索からサイト内導線まで「迷わない体験」を貫く
これらが揃うことで、ユーザーは「このブランドは信頼できる」と感じ、自然に行動を起こします。デュアルデザイン設計は、検索から行動、さらにブランドの記憶に至るまでを一貫して設計できるフレームワークなのです。
導入メリット(CVR改善・離脱率低下・ブランド価値向上)
デュアルデザイン設計を導入することで得られる最大のメリットは「成果に直結する体験の提供」です。スマホで予約や購入がスムーズに完了するだけでなく、離脱率の低下やブランド価値の向上にもつながります。BtoCサイトでは、ほんの数秒の使いにくさがCVRに直結するため、従来の縮小レスポンシブでは成果が頭打ちになるケースが少なくありません。
そこでモバイル専用に最適化された意思決定設計を行うことで、ユーザーは「迷わず行動できる」という安心感を得ます。また近年はGoogle検索だけでなく、SNSのハッシュタグ検索から訪れるユーザーが増えているため、直感的なUI・UXがブランドの信頼感を高める重要な要素となっています。
CVR改善の具体的効果
デュアルデザイン設計によって、スマホでの行動導線が短縮され、CVRは大幅に改善します。たとえば飲食サイトで「空席確認と即予約」をワンタップで実現できるようにした結果、予約完了率が向上した事例もあります。ECサイトでは「購入ボタンを固定表示」「決済フローを短縮」することでカゴ落ちを防止でき、モバイル経由の売上増加につながります。
さらにSNS検索から流入したユーザーにとっては「わかりやすさ」と「即行動」のしやすさがブランドへの信頼につながり、そのままコンバージョンに直結します。
離脱率低下とUX改善
従来の縮小レスポンシブでは「目的の情報に辿り着くまでにスクロールが長すぎる」という課題がありました。デュアルデザイン設計では、ユーザーが求める情報を優先順位づけして配置するため、途中離脱の要因を大幅に減らせます。
特にSNS検索から流入したユーザーは「数秒で欲しい情報が見つからないと離脱する」傾向が強く、ここでUXの差が顕著に出ます。最初からモバイルに最適化された情報設計を行うことで、滞在時間が伸び、結果としてSEOやSNSの評価も高まるのです。
ブランド価値の向上
スマホでの体験は、そのままブランドの印象を決定づけます。ユーザーが「使いやすい」「ストレスなく行動できる」と感じれば、それはブランドの信頼感として積み重なります。逆に操作しづらいサイトは「この会社は古い」「不親切」というネガティブな印象を与えかねません。
デュアルデザイン設計は、単なるUI改善ではなく「ブランドを体験として伝える仕組み」として機能します。特にSNSから訪れたユーザーは、初めてそのブランドに触れるケースが多いため、スムーズな体験が「また利用したい」「シェアしたい」というポジティブな記憶へと変わります。
まとめ|体験 × 設計でBtoCサイトの成果を最大化する
デュアルデザイン設計は、単なる「スマホ対応」や「レスポンシブ最適化」を超えた、新しいホームページ制作の思想です。
PCとモバイルを同じ構造で扱うのではなく、それぞれの役割と文脈に合わせて切り分け、ユーザーが迷わず行動できる体験をつくることに重点を置きます。
特にBtoCサイトでは、ユーザーが意思決定する場はスマホであり、その出発点はGoogle検索だけでなく SNSハッシュタグ検索(#福岡ランチ、#髪質改善、#福岡旅行 など) にも広がっています。こうした多様な検索起点を一貫した体験設計につなげることが、成果を最大化するカギなのです。
デュアルデザイン設計が示す未来
今後のWeb制作においては「情報を載せるだけのホームページ」では成果は期待できません。ユーザーは短時間で判断し、快適に行動できるサイトだけを選びます。デュアルデザイン設計は、意思決定を支援するUI/UXをモバイル中心に組み立て、PCでは検討・比較を支える構造を持たせるという二軸設計です。これにより、離脱を減らし、CVRを高め、さらにブランド価値の向上へとつなげられます。
詳細はご相談ください
本記事ではデュアルデザイン設計の背景やメリットを解説しましたが、実際の導入は業種や事業モデルによって最適解が異なります。飲食、美容、EC、旅行――それぞれで求められるUX設計は違います。自社サイトにとって何が成果につながるのかを見極めるには、専門的な分析と設計が不可欠です。
詳細な設計方法や改善のアプローチについては、ぜひWebaxisまでご相談ください。 貴社のBtoCサイトが「検索から始まるブランド体験」を最大化できるよう、伴走型でご提案いたします。
BtoCサイトにおけるモバイルファーストやデュアルデザイン設計の考え方は、単体の手法だけでは成果につながりません。
検索から始まるユーザー体験を一貫して設計するためには、全体像を理解したうえで、自社サイトに最適な施策を選択することが大切です。
▶ 関連記事: