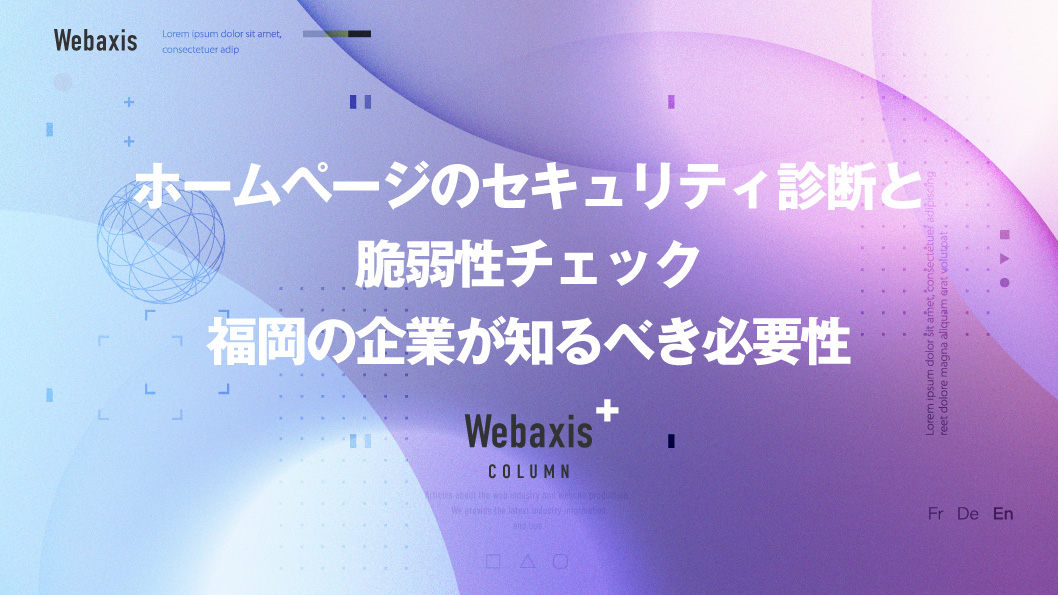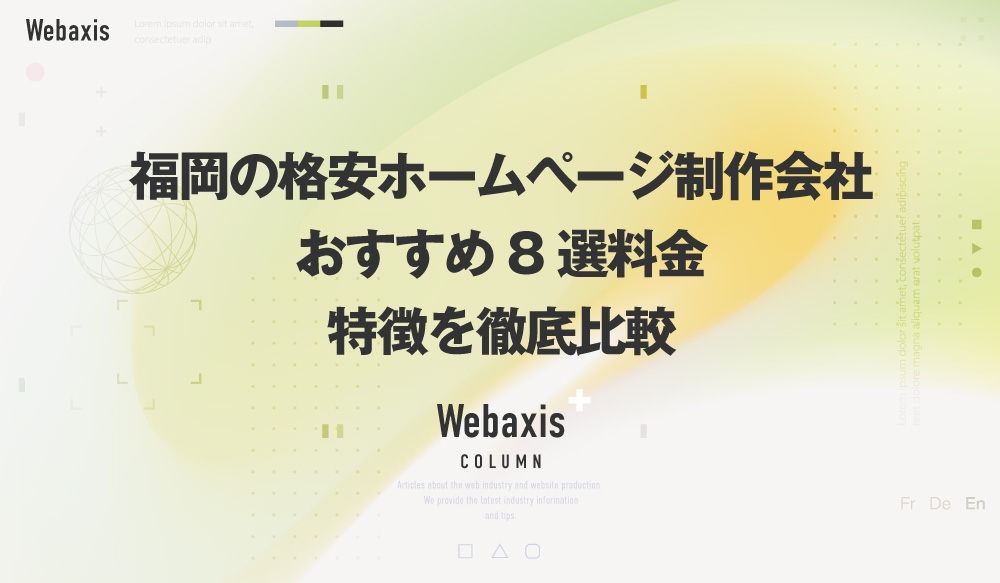従業員のセキュリティ教育と意識向上|福岡の企業が実践すべき対策
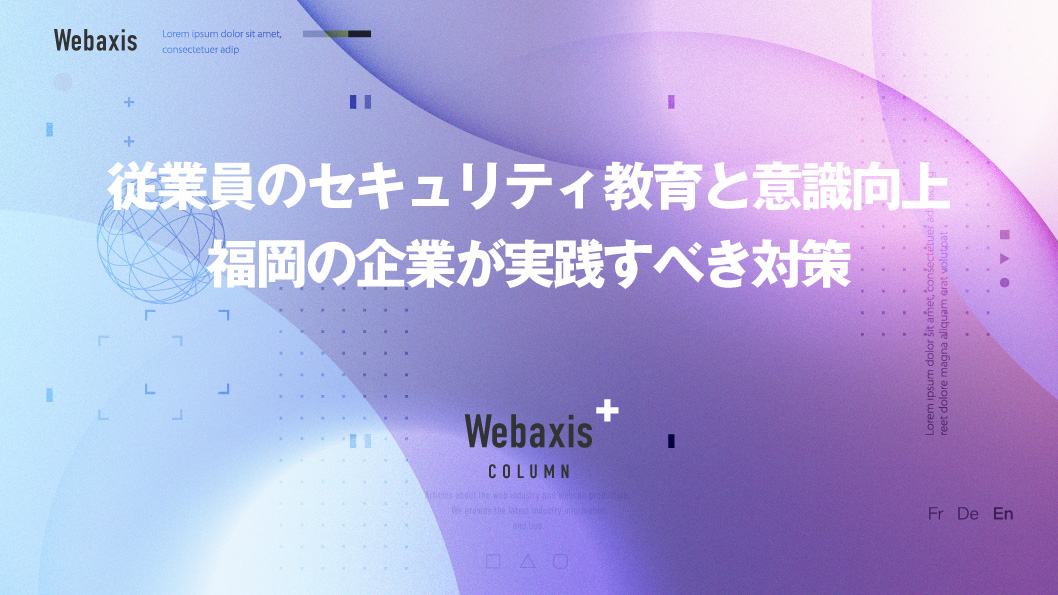
福岡でホームページを運営する企業にとって、従業員のセキュリティ教育とセキュリティ意識の向上は、ホームページを守るために欠かせません。実は、ホームページへの不正アクセスや情報漏洩の多くは、従業員の操作ミスや不注意から発生しています。
経済産業省が2025年5月に発表した調査によると、**回答企業の64%が従業員に対するセキュリティ教育を「特に実施していない」**と回答しました。一方で、日本ネットワークセキュリティ協会の調査では、人的要因で情報が漏洩したケースは全体の60%を上回るという結果が出ています。
ホームページの管理画面に誰でもアクセスできる、パスワードが簡単すぎる、更新作業でミスをする。こうした従業員のちょっとした不注意が、ホームページのセキュリティを脅かします。この記事では、福岡の企業がホームページ運用における従業員のセキュリティ教育を簡単に始められる方法と、セキュリティ意識を向上させるコツを解説します。
目次
ホームページ運用でなぜ従業員教育が重要なのか
ホームページのトラブルは「人」が原因
高価なセキュリティソフトを導入しても、ホームページを操作する従業員のセキュリティ意識が低ければ意味がありません。ホームページの管理画面のパスワードを付箋に書いてパソコンに貼っている、複数の従業員が同じIDとパスワードを共有している、更新作業で間違えて重要なファイルを削除してしまう。こうした人的ミスが、ホームページのセキュリティ問題につながります。
東京商工リサーチが2024年1月に発表した調査結果では、2023年の個人情報漏えい事故175件のうち、「誤表示・誤送信」が24.5%、「不正持ち出し・盗難」が13.7%を占めています。ホームページ運用でも、従業員が誤って顧客情報を公開してしまう、管理画面のパスワードを漏らしてしまうといった事例が実際に起きています。
福岡の企業でホームページを運用するなら、従業員のセキュリティ教育を実施することで、こうした人的ミスを大幅に減らすことができます。ホームページのセキュリティ教育の重要性は、技術的な対策と同じくらい高いのです。
ホームページの被害は信用問題に直結
「うちのホームページは小規模だから大丈夫」と思っていませんか?総務省による令和5年情報通信白書では、セキュリティインシデントによる1組織あたりの年間平均被害額は約3億2,850万円と報告されています。
特にホームページが改ざんされたり、顧客情報が漏洩したりすると、企業の信用は一気に失墜します。福岡で地域密着型のビジネスを展開している企業にとって、地元での評判は何よりも大切です。従業員のセキュリティ教育にかけるコストは、こうした信用の失墜を防ぐための安い投資と言えるでしょう。
福岡の中小企業でも、ホームページ運用における従業員のセキュリティ意識向上に取り組むことで、将来的な大きな損失を防ぐことができます。
ホームページ運用で従業員に教えるべきこと
WordPressの管理画面は誰でも触らせない
ホームページがWordPressで作られている場合、管理画面にアクセスできる従業員を必要最小限に絞ることが重要です。ホームページのセキュリティ教育の第一歩は、「誰が何をできるか」を明確にすることです。
WordPressには、管理者、編集者、投稿者、寄稿者、購読者といった役割(権限)があります。ブログ記事を書くだけの従業員には「投稿者」の権限、プラグインやテーマを触る必要がない従業員には「編集者」の権限を与えるといった具合に、必要最小限の権限だけを付与します。
全従業員に「管理者」権限を与えてしまうと、誰かが間違えてプラグインを削除したり、重要な設定を変更したりする危険性が高まります。従業員のセキュリティ意識を高めるためにも、「自分に与えられた権限の範囲で作業する」というルールを徹底しましょう。
パスワードは絶対に共有しない
ホームページ運用で最もやってはいけないのが、管理画面のパスワードを複数の従業員で共有することです。「みんなで同じパスワードを使えば楽だから」という理由で共有している企業もありますが、これはセキュリティ上非常に危険です。
パスワードを共有していると、誰がいつホームページを操作したのか追跡できません。もし問題が発生しても、原因を特定できなくなります。また、退職した従業員がパスワードを覚えていれば、退職後もホームページにアクセスできてしまいます。
従業員のセキュリティ教育では、必ず個別のアカウントを作成し、それぞれが自分専用のパスワードを設定することの重要性を伝えましょう。パスワードは「できるだけ長く、推測されにくいもの」にすることも併せて教育します。
更新作業の前にバックアップを確認
ホームページの更新作業を担当する従業員には、「バックアップがあるか確認してから作業する」という習慣をつけてもらいましょう。ホームページのセキュリティ教育の一環として、バックアップの重要性も伝えます。
プラグインを更新する、テーマを変更する、大きな修正を加える。こうした作業の前には必ずバックアップを取っておくことで、万が一問題が発生しても元に戻せます。自動バックアップを設定していても、重要な作業の前には手動でもバックアップを取る習慣をつけると安心です。
従業員のセキュリティ意識向上には、「何かあったときにどう対処するか」を事前に考える習慣をつけてもらうことも含まれます。
不審なメールには絶対に反応しない
ホームページを運用していると、「WordPressのアップデートが必要です」「あなたのサイトがハッキングされました」といった不審なメールが届くことがあります。従業員のセキュリティ教育では、こうしたメールに反応しないことを徹底します。
特に、メールに書かれたリンクをクリックしたり、添付ファイルを開いたりするのは危険です。本物に見えるメールでも、実はフィッシング詐欺の可能性があります。WordPressやプラグインの更新は、メールのリンクからではなく、必ず管理画面から直接行うようにしましょう。
ホームページのセキュリティ意識を高めるには、「疑わしいと思ったら、まず上司やIT担当者に相談する」というルールを作っておくことが大切です。
ホームページ運用でセキュリティ意識を高める方法
ルールを明文化して共有する
ホームページのセキュリティ教育を効果的にするには、ルールを明文化して従業員に共有することが重要です。口頭で伝えただけでは忘れてしまうので、簡単なマニュアルを作りましょう。
マニュアルには、誰がホームページの管理画面にアクセスできるか、パスワードはどう管理するか、更新作業の前に何をチェックするか、問題が起きたときは誰に連絡するか、といった基本的なルールを書いておきます。A4用紙1〜2枚程度の簡単なものでも十分です。
このマニュアルを新しくホームページの更新を担当する従業員に渡し、一緒に内容を確認することで、従業員のセキュリティ意識を高めることができます。福岡の企業でも、こうした簡単なマニュアルから始めてみましょう。
定期的にパスワードを変更する習慣をつける
ホームページの管理画面のパスワードは、定期的に変更する習慣をつけましょう。従業員のセキュリティ教育では、「3ヶ月に1回はパスワードを変更する」といった具体的なルールを決めます。
特に、従業員が退職するときは必ずパスワードを変更することを徹底します。退職した従業員が悪意を持ってホームページにアクセスすることはないかもしれませんが、万が一のリスクを避けるためにも、パスワード変更は必須です。
また、「パスワードをブラウザに保存しない」「付箋に書いてパソコンに貼らない」といった基本的なルールも、ホームページのセキュリティ意識向上のために伝えておきましょう。
更新作業の記録を残す
誰がいつホームページを更新したのか、簡単な記録を残す習慣をつけることも、従業員のセキュリティ意識向上につながります。Excelやスプレッドシートで簡単な更新記録表を作り、更新日、担当者、更新内容を記入してもらいましょう。
この記録があると、問題が発生したときに「誰がいつ何をしたのか」がすぐにわかります。また、従業員自身も「記録に残る」と意識することで、より慎重に作業するようになります。
ホームページのセキュリティ教育では、こうした「記録を残す」という習慣の重要性も伝えましょう。
問題が起きたときの連絡先を明確にする
ホームページで何か問題が起きたとき、従業員がパニックにならないよう、あらかじめ連絡先を明確にしておきます。「ホームページが表示されない」「変な画面が出た」「操作ミスをしてしまった」といったときに、誰に連絡すればいいのか分かるようにしておきましょう。
連絡先は、社内のIT担当者、上司、ホームページ制作会社など、状況に応じて複数用意しておくと安心です。この連絡先リストをマニュアルに載せたり、デスクに貼っておいたりすることで、緊急時にすぐに対応できます。
従業員のセキュリティ意識向上には、「困ったときは一人で抱え込まず、すぐに相談する」という文化を作ることも含まれます。
福岡の企業が使える無料のセキュリティ教育資料
IPAの「情報セキュリティ10大脅威」
福岡の企業がホームページのセキュリティ教育を始めるとき、IPA(情報処理推進機構)が無料で提供している「情報セキュリティ10大脅威」を活用しましょう。この資料では、その年に話題になったセキュリティ事件がランキング形式でまとめられています。
ホームページ運用に関連する脅威も多く取り上げられているので、従業員に「こんな危険があるんだ」と実感してもらえます。年に1回、この資料を使って簡単な勉強会を開くだけでも、従業員のセキュリティ意識向上に効果的です。
WordPressの公式ドキュメント
WordPressでホームページを運用している場合、WordPress公式サイトのドキュメントも参考になります。セキュリティに関するページでは、基本的な対策方法が日本語で説明されています。
従業員に「WordPressのセキュリティって何?」と聞かれたときに、この公式ドキュメントを見せながら説明すれば、ホームページのセキュリティ教育の重要性が伝わりやすくなります。
まとめ:ホームページを守るのは従業員のセキュリティ意識
ホームページ運用における従業員のセキュリティ教育の重要性とセキュリティ意識向上は、福岡の企業がホームページを守るために欠かせません。経済産業省の調査によると、回答企業の64%が従業員に対するセキュリティ教育を「特に実施していない」という現状がありますが、人的要因による情報漏洩は全体の60%を上回ります。
福岡の企業がホームページ運用における従業員のセキュリティ教育を効果的に実施し、セキュリティ意識を向上させるには、以下の実践的な対策が重要です。
まず、ホームページの管理画面にアクセスできる従業員を必要最小限に絞り、それぞれに適切な権限を与えます。パスワードは絶対に共有せず、個別のアカウントを作成します。更新作業の前にはバックアップを確認する習慣をつけ、不審なメールには反応しない教育を徹底します。
次に、ルールを明文化して従業員に共有し、定期的なパスワード変更の習慣をつけます。更新作業の記録を残し、問題が起きたときの連絡先を明確にしておくことで、従業員のセキュリティ意識が自然と高まります。
総務省のデータによると、セキュリティインシデントによる1組織あたりの年間平均被害額は約3億2,850万円に上ります。従業員のセキュリティ教育とセキュリティ意識向上により、これらの損失を大幅に削減できます。
福岡でホームページを運営する企業は、従業員のセキュリティ教育の重要性を今すぐ認識し、ホームページのセキュリティ意識向上のための施策を実践しましょう。この記事で紹介したセキュリティ教育方法を実践し、従業員のセキュリティ意識を高めることで、ホームページを安全に運用できます。
▶ 関連記事:
- 従業員のセキュリティ教育と意識向上|福岡の企業が実践すべき対策
- SSL化(https化)は必須|福岡の企業ホームページで今すぐ対応すべき理由
- 福岡の中小企業が知るべきホームページセキュリティ対策の基本【2025年版】
- WordPressのセキュリティ対策|福岡の企業サイトを守る7つの必須設定
- 不正アクセスとホームページ改ざんを防ぐ|福岡の企業が実践すべき対策
- ホームページのバックアップと復旧体制|福岡の企業が知るべきデータ保護の重要性
- ホームページのセキュリティ対策費用と投資効果|福岡の企業が知るべきコスト
- ホームページのセキュリティ診断と脆弱性チェック|福岡の企業が知るべき必要性
福岡でホームページ運用における従業員のセキュリティ教育にお悩みの方へ
Webaxisでは、ホームページ運用における従業員のセキュリティ教育の重要性を理解した効果的な教育プログラムの構築をサポートしています。福岡の企業の従業員のセキュリティ意識を向上させ、ホームページを安全に運用するための最適なソリューションをご提案します。