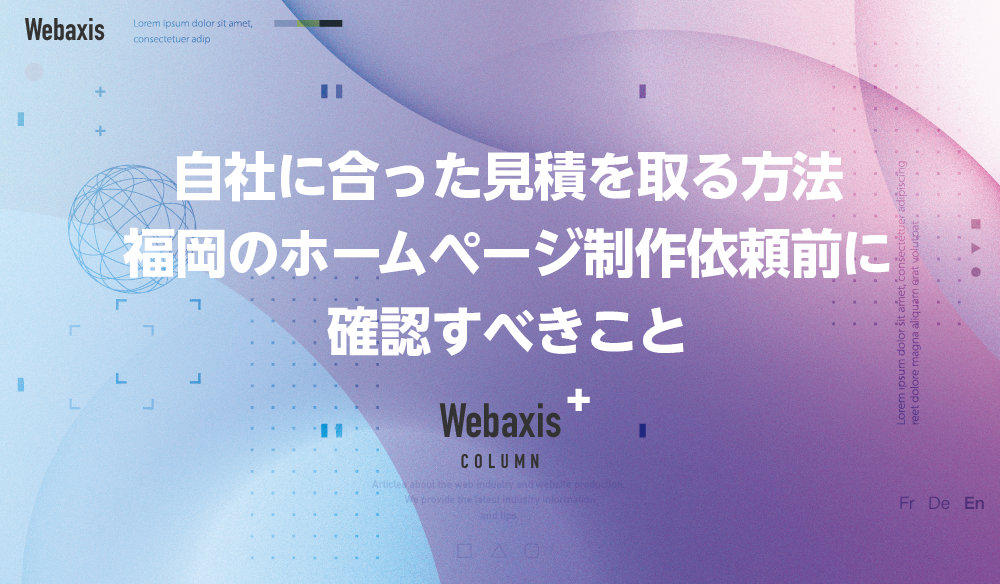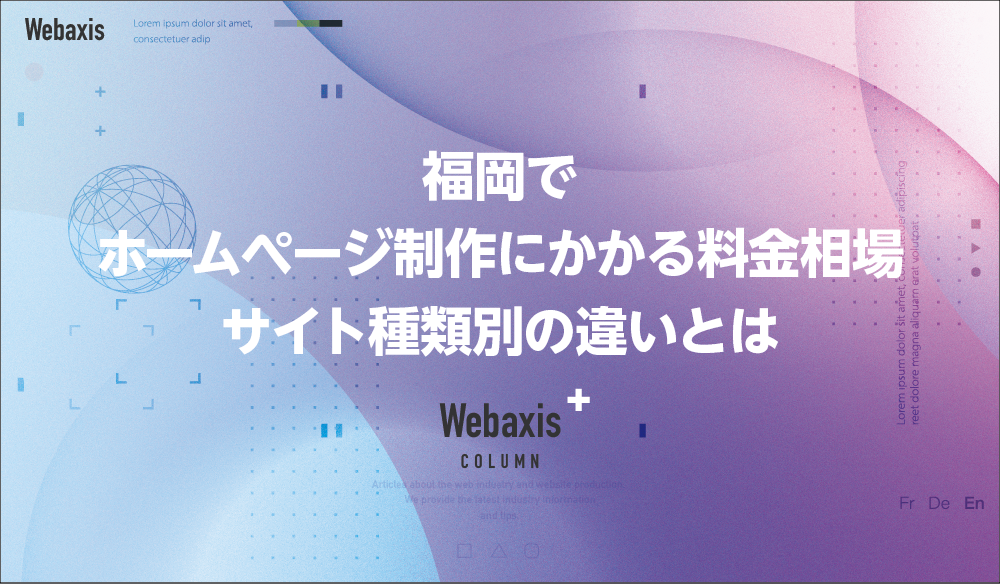福岡で使える補助金・助成金でホームページ制作費用を抑える方法【2025年】
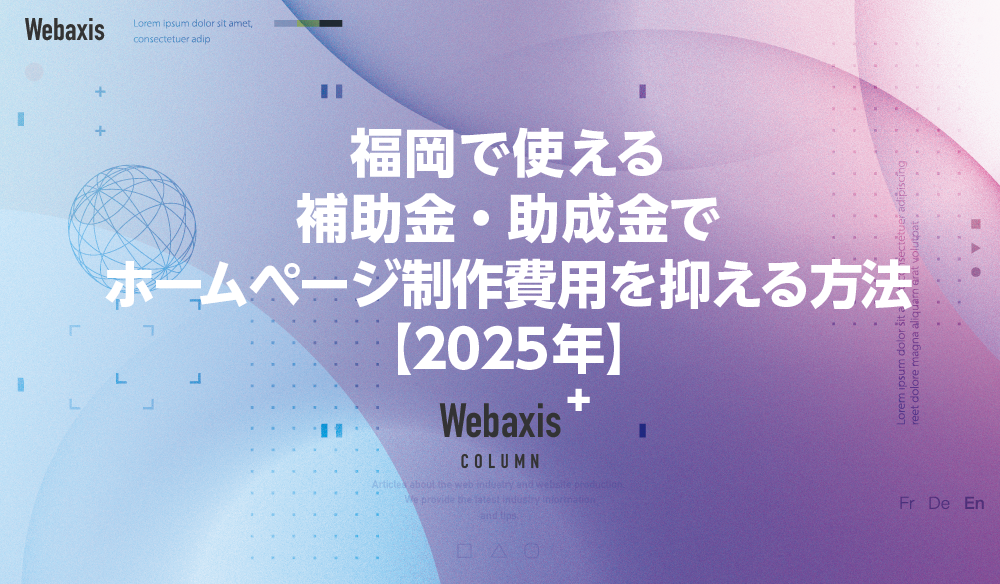
ホームページ制作を検討する際、気になるのがその費用負担です。とくに中小企業や個人事業主にとって、数十万円〜数百万円にも及ぶ制作費用は大きな投資となるため、資金調達やコスト削減は非常に重要なポイントとなります。そこで注目されているのが「補助金」や「助成金」の活用です。
2025年現在、福岡県内の企業や個人事業主が活用できるホームページ制作関連の補助制度は複数存在しており、それらを上手に利用することで、自己負担を大幅に軽減することが可能です。本記事では、福岡で活用できる補助金・助成金制度の最新情報を紹介しながら、ホームページ制作費用を抑えるための実践的な方法を解説します。
目次
ホームページ制作に補助金・助成金が使える理由とは?
2025年現在、福岡をはじめとする全国の自治体や中小企業支援機関では、「デジタル化」「業務効率化」「販路拡大」などの観点から、ホームページ制作に対して補助金や助成金を適用する制度が数多く展開されています。これまで広告費やチラシ制作などの“紙”中心だった広報活動も、コロナ禍を機に一気にオンライン化が進み、ホームページが事業活動の基盤として認識されるようになりました。そのため、単なる情報掲載ページではなく、「問い合わせ獲得」や「EC販売」「人材採用」「顧客管理」といった事業成果に直結するサイトづくりが支援対象とされるケースが増えています。
では、なぜホームページ制作に補助金や助成金が使えるのか?どのような制度の枠組みで対象とされているのか?本章では、制度設計の背景とともに「経費区分」や活用の前提条件をわかりやすく解説します。
中小企業のDX支援とデジタル化促進の流れ
補助金や助成金の根本的な目的は「地域経済の活性化」や「中小企業の経営基盤の強化」にあります。特にここ数年で強調されているのが“DX(デジタルトランスフォーメーション)”です。政府は中小企業庁や経済産業省を通じて、「ITを活用して業務を効率化し、収益向上を図る企業」に対して積極的に支援を行っており、ホームページ制作もその対象として位置付けられるようになっています。
具体的には、以下のような観点が補助対象として評価されます:
- オンラインでの受注・販売・予約受付(EC・予約サイト)
- 採用ページの拡充と応募管理のデジタル化
- 多言語化によるインバウンド対応
- スマートフォン最適化によるユーザー対応強化
ただし、単なる名刺代わりの「会社概要ページ」や、更新頻度のない静的サイトだけでは補助対象外となることも多いため、「ビジネス課題を解決するためのデジタル投資であること」が前提になります。つまり、“DXを目的とした機能性あるホームページ設計”が補助金活用の大前提であり、そこにWeb制作会社の提案力や設計力が問われるのです。
補助金・助成金が適用される「経費区分」とは
補助金制度では、支出項目ごとに「補助対象経費」として認められるかどうかが明確に区分されています。ホームページ制作に関しては、多くの制度で「広報費」または「外注費」などの形で対象とされることが一般的です。
代表的な対象経費の例
| 経費項目 | 補助対象になりやすい内容 |
|---|---|
| 外注費 | ホームページ制作費(デザイン・コーディングなど) |
| 広報費 | Web広告バナー制作、ランディングページ作成 |
| 専門家経費 | Web戦略やUI/UX設計に関するコンサルティング料 |
| ソフトウェア購入費 | CMS導入やアクセス解析ツールなどの導入費用 |
特に、持続化補助金では「販路開拓等の取り組み」に該当するかどうか、IT導入補助金では「業務効率化や生産性向上」に繋がる構造かどうかが判断軸となります。制作目的が曖昧だったり、企画書・見積書に「成果を出すための具体的な設計意図」が盛り込まれていない場合は、審査で不利になることもあります。
Webaxisでは、これらの補助対象経費を踏まえた上で、見積書や仕様書に「補助金申請で通りやすい構成」を盛り込むことが可能です。あくまで申請代行は行いませんが、審査で問われる“合理性と戦略性”のある資料提供には対応しています。
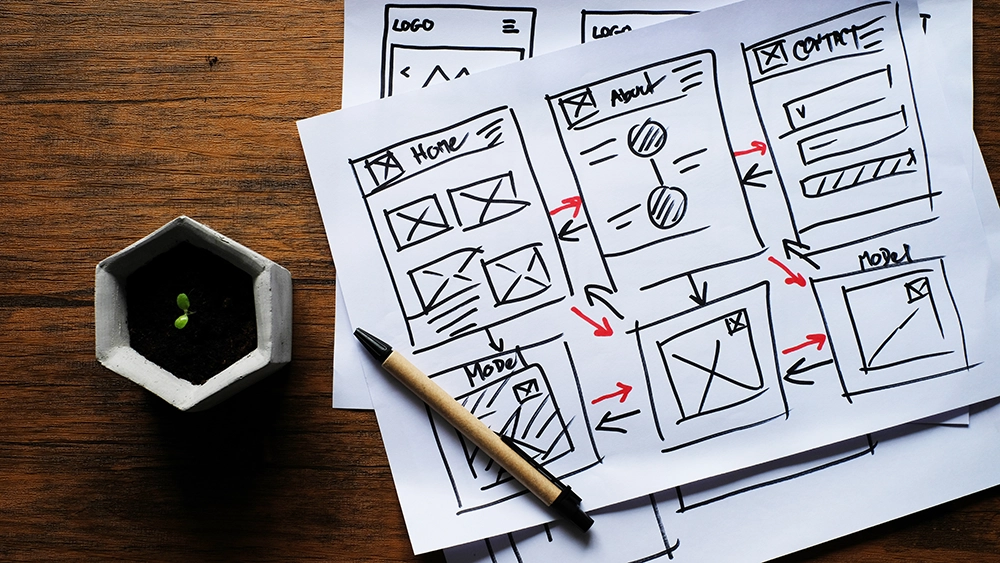
福岡で活用できる主な補助金・助成金制度【2025年版】
福岡県内でホームページ制作費用を抑えるうえで活用できる代表的な補助金・助成金制度は、国の制度に加え、県や市町村が独自に展開する支援策も存在します。重要なのは「自社の目的や成長フェーズに合った制度を選ぶ」ことです。ここでは2025年時点で注目されている制度をピックアップし、それぞれの特徴と対象経費、申請のポイントについて解説します。
小規模事業者持続化補助金(一般型・成長分野展開枠)
「持続化補助金」は、販路開拓や業務効率化の取り組みを行う小規模事業者を支援する代表的な制度です。商工会議所または商工会のサポートを受けながら申請でき、申請書のブラッシュアップも支援対象になるため、初めて補助金にチャレンジする事業者にとって最もハードルが低い制度と言えるでしょう。
【2025年版の注目ポイント】
- 一般型に加え「成長分野展開枠」では上限額が最大200万円に
- 申請要件に「経営計画書」と「今後の販路開拓方針」の明記が必要
- ホームページ制作費は「広報費」として補助対象
- ロゴ・チラシ・動画制作も対象に含まれるため、ブランド整備との併用も可能
対象となる福岡の事業者例
- 地場で展開する飲食業や小売業、地域密着型の美容・介護サービス業
- BtoC領域で自社の魅力を発信し、新たな顧客獲得を図りたい企業
制作内容や見積書が事業目的と整合していれば、採択率は比較的高く、Webaxisでもこれまで多くの制作案件で同制度に基づく資料提供を行っています。
IT導入補助金(デジタル化基盤導入枠)
IT導入補助金は、中小企業の業務効率化やDX推進のためのツール導入を支援する制度です。特に「デジタル化基盤導入枠」では、ホームページ制作やECサイト構築に加え、クラウド会計や顧客管理システム(CRM)との連携なども補助対象に含まれます。
【2025年の特徴】
- 通常枠(A/B類型)とは別に、デジタル基盤整備に特化した枠を設置
- 補助率は最大2/3、補助上限は最大450万円
- 「CMS構築」や「セキュリティ対策」なども加点要素となる
対象となるホームページ制作内容:
- EC機能付きのネットショップ構築
- 問い合わせフォームと業務システム連動型のWebサイト
- BtoB企業向けの資料ダウンロード・顧客管理連携サイト
補助金の交付を受けるには、「IT導入支援事業者」に登録された制作会社が実施する必要があります。WebaxisはIT導入支援事業者ではありませんが、他社と連携した形での要件設計や、補助対象とみなされるサイト構成の提案、資料作成支援に対応可能です。
福岡県・市町村の独自助成制度(最新動向を紹介)
福岡県内では、県・市町村単位でも地域特性に即したデジタル支援が進められています。以下に、2025年時点で活用できる可能性のある自治体独自制度を紹介します(※年度ごとに更新されるため、申請前の最新確認が必須です)。
| 自治体 | 制度名例 | 特徴 |
|---|---|---|
| 福岡県 | 中小企業デジタル化支援事業 | 中小企業の業務効率化に必要なIT導入に最大50万円補助(年1回程度) |
| 北九州市 | DX推進補助金 | デジタルマーケティング強化を目的としたWeb施策全般が対象(令和6年度も継続の見込み) |
| 久留米市 | ホームページ等作成支援補助金 | 創業後間もない事業者向けに最大20万円補助。創業支援施策と連携 |
| 糸島市 | 小規模事業者等支援補助金 | 地域商工会経由での申請を通じ、販促物・Web制作が対象に |
活用のポイント:
- 申請時期や採択件数が少ないため「早期の情報収集」が必須
- 各自治体の商工労働課・産業振興課のページを定期的にチェック
- Webaxisでは、自治体名・制度名を指定しての見積書作成が可能
これらの制度は、事業規模が小さい企業やスタートアップにとって、初期投資を抑えながらブランド強化・顧客獲得に踏み出すための心強い支援となります。
補助金・助成金を活用したホームページ制作の進め方
補助金・助成金を利用してホームページを制作する場合、通常のWeb制作と比較して、申請・審査・報告といった追加の工程が発生します。これらを踏まえたうえで、「制度に適合する形で事業計画と制作スケジュールを立てること」が成功のカギです。
Webaxisでは補助金申請の代行業務は行っていませんが、対象制度に応じた仕様設計・見積書の提供など、申請準備をスムーズに進めるサポートが可能です。
申請前に確認すべき「対象要件」と「事業計画」
補助金制度には、それぞれ異なる申請要件や対象経費の定義があります。事前確認を怠ると、制作したにもかかわらず補助対象外となるケースもあるため、以下のポイントを押さえておく必要があります。
1. ホームページの目的が制度と一致しているか?
- 持続化補助金:販路開拓・認知拡大が目的か
- IT導入補助金:業務効率化やデジタル基盤整備が主軸か
2. 補助対象となる「経費項目」に合致しているか?
- CMS構築、デザイン、レスポンシブ対応、UI設計などが対象になることが多い
- 単なる更新作業や既存サイトの修正のみは対象外になりやすい
3. 事業計画書との整合性があるか?
- どのような課題があり、ホームページを使ってどう解決するか
- 制作後にどのような成果・波及効果が期待できるか
このフェーズで作り込みが甘いと、申請自体が通らないリスクがあるため、Webaxisでは「補助金の申請目的に即した提案書・構成案」を制作に先立ってご提示することも可能です。
採択後の流れと注意点(制作スケジュールの組み方)
補助金が無事に採択された後は、指定された期間内にホームページを完成させる必要があります。このとき、「実施期限内に成果物の納品・支払い・報告を完了させること」が原則です。
採択後の主な流れ
- 交付決定通知の受領(ここから着手が可能)
- Web制作会社と本契約 → 着手
- 制作スケジュールの確定 → 納品日を制度に合わせる
- 実績報告書の提出(納品書・支払い証明書の添付が必要)
- 補助金の確定・入金(最終的な審査あり)
スケジュール上の注意点
- 制作期間は約2〜4ヶ月が一般的。短納期が求められる制度では「LP形式」「段階リリース」など柔軟な設計が有効。
- 「納品=公開」ではなく、「制作完了=報告できる形」になっていればOKの制度もある。
- 発注・契約・支払いのタイミングが制度のルールと一致していないと、補助対象外になるリスクがある。
制作開始のタイミングを「交付決定通知以降」に設定するのが原則であり、申請前に準備していたとしても、正式発注や着手は通知後に行う必要があります。Webaxisではこのような制度特有の制約も踏まえたスケジュール設計をご提案し、確実に補助対象となるよう支援を行っています。

補助金活用の注意点と「代行業者」への依存リスク
補助金を活用したホームページ制作においては、申請から制作、報告まで多くのプロセスが絡みます。そのため、「補助金申請代行」を掲げる業者に丸ごと任せようとする企業も少なくありません。しかし、実務の現場では、代行業者への“過度な依存”によってトラブルや目的との乖離が生じるケースが後を絶ちません。
ここでは、補助金を使ったWeb制作を成功に導くために、注意すべきポイントとWebaxisのスタンスをお伝えします。
代行業者に丸投げすることで発生しやすいトラブル
補助金の申請を「通すこと」だけにフォーカスした業者は、制作目的や事業成果への視点が欠如していることがあります。特に以下のようなケースには注意が必要です。
1. 採択後の“制作品質”が不透明
- 申請時はきれいな構成案を提示されたが、採択後はテンプレート的な低品質サイトを納品された。
- 「補助金ありき」の提案で、本来目指していたブランディングや成果導線の構築がなされない。
2. 制作スケジュールと制度条件が噛み合わない
- 交付決定通知前に着手してしまい、対象外扱いになる。
- 実績報告の期限に間に合わず、補助金が不支給となる。
3. コミュニケーションの不整合
- 制作会社と申請代行業者が別のため、認識ズレが発生しやすく、発注者が板挟みに。
- 誰が責任を持つのか不明確なままプロジェクトが進行してしまう。
4. 事業主側が制度を理解できていないまま進む
- 「全部お任せ」で制度の意図やルールを把握しないまま契約・発注を進めてしまう。
- 万一の不支給時に備えたリスク対策や代替案が用意されていない。
これらのリスクは、結果的に“補助金が出てもビジネス的成果につながらない”という最悪の結末を招く可能性があります。
Webaxisのスタンスと「伴走型サポート」の考え方
Webaxisでは、補助金制度を「ビジネスを成長させるための手段」と位置づけており、制度の利用を前提とした“目的設計”から伴走型で支援します。
私たちが大切にしている姿勢
- 補助金の有無に関わらず「成果につながるホームページ」を第一に設計
- 制度のルールに即した見積書や仕様書の作成支援は可能
- 申請そのものは外部の専門家(社労士・行政書士等)との連携を推奨
- 事業主が“制度を理解したうえで選択できる”状態を重視
また、制度の申請や実績報告において必要な「設計書」「要件定義」「仕様書」などのドキュメントについては、制作フェーズの中でご希望に応じてご用意可能です。過去に補助金申請で実績のある構成・スケジュールをもとに、成功確度の高い計画をご提案いたします。
「丸投げ」ではなく、「共に理解しながら進める」。それがWebaxisの補助金活用に対するスタンスです。
Webaxisが提供できる補助金・助成金サポートとは
補助金や助成金を活用してホームページ制作を行う際、制度に沿った書類作成や根拠づけのある事業計画の提示が重要です。Webaxisでは、申請の代行は行いませんが、制度の要件に対応した見積書や構成資料の作成支援を通じて、事業者様の円滑な申請をサポートします。
ここでは、私たちが提供できる2つの具体的な支援内容についてご紹介します。
申請用の見積書・構成資料の作成支援
補助金申請においては、「どのような内容のWebサイトを制作するのか」「その費用の内訳はどのようになっているのか」といった情報を、制度要件に合致する形で明示する必要があります。
Webaxisでは以下のような資料の作成支援を行っています:
- 制度別の様式やルールに対応した見積書の作成 例:IT導入補助金の区分に対応した項目分け、持続化補助金に適合する業務分担明細の記載など
- サイト構成図やワイヤーフレームの作成支援 補助対象となる「機能」や「仕様」の明確化をサポートし、審査側が事業目的と実施内容を判断しやすくします。
- スケジュール表・実施計画のたたき台提供 交付決定前の着手禁止など、制度ルールに配慮した制作スケジュール案を提示します。
これらの資料は、単に補助金を獲得するための形式的な書類ではなく、「成果を生むWebサイト設計」そのものの一部としてご提供しています。
「ブランディング設計書」を活かした根拠資料の提供
Webaxisのホームページ制作では、ブランディング視点に基づく「設計書」を必ず作成します。この設計書は、補助金申請においても事業計画書の根拠資料として非常に有効です。
たとえば、
- 「企業の強みやビジョンに基づくブランド構築方針」 → 補助金制度における“経営の革新性”や“販路開拓”の裏付け資料に。
- 「ユーザー導線・UI/UX設計図」 → 成果指標(KPI)の妥当性や施策の実現性を説明する材料に。
- 「コンテンツ戦略案・SEO設計」 → デジタル活用による業務効率化・集客強化の内容として記載可能。
補助金の審査においては、「単なる見た目」や「ツール導入」以上に、明確な“成果の筋道”が求められます。Webaxisのブランディング設計書は、その裏付けとして活用できる設計ドキュメントです。
✅ POINT
Webaxisでは「申請サポート」として、制度に応じた柔軟な資料提供が可能です。特に、要件が複雑な補助金(例:IT導入補助金や自治体独自制度など)では、事前相談の段階からスムーズに資料設計を進められるよう、専門スタッフが伴走します。
このように、Webaxisは「制作のプロ」として、制度要件と事業目的の両方を見据えた支援を行っています。補助金ありきではなく、“成果ありき”の制作を目指す事業者様にとって、確かな土台となるサポートを提供します。
補助金に頼りすぎない制作計画の立て方
補助金や助成金を活用できることは、ホームページ制作を進める上での大きな追い風となります。しかし一方で、「助成がなければ実現できない」設計に陥ると、事業の本質的な価値や成長性を損なう危険性も孕んでいます。
ここでは、補助金に依存せず、長期的な成果を見据えた制作計画の立て方を2つの視点から解説します。
初期費用・月額費用・運用工数を俯瞰した全体設計
補助金によってカバーされるのは、たいていの場合「初期制作費用」の一部にすぎません。運用フェーズに入ってからのコストと人的リソースは、事業者自身が担うことになります。
だからこそ、制作段階から以下のような「全体像」を意識する必要があります。
- 初期費用の内訳の透明性 → 補助金の対象外となる要素(例:写真撮影、ロゴ制作、取材費など)も明示しておくことで、後の資金計画にズレが生まれません。
- 月額費用(保守・サーバー・CMS使用料など)の算定 → 補助後も継続的に必要となるランニングコストを明確に把握し、固定費の増加リスクを最小限に抑えます。
- 社内工数や運用体制の設計 → 制作後のコンテンツ更新・SNS連携・問い合わせ対応など、運用に必要な社内リソースや役割分担も初期段階から検討しましょう。
このように、初期投資+月次運用+社内リソースという3軸で全体設計を行うことで、「補助金ありき」ではない持続可能な制作計画が実現します。
「助成ありき」ではなく成果を重視した戦略設計へ
補助金や助成金は、あくまで**“目的を実現するための手段”**です。本来の目的は、売上向上、ブランド価値の向上、採用強化など、事業の成果に結びつくWeb活用であるべきです。
そのため、制作の段階では以下のような戦略的視点が求められます。
- 補助金がなくても「必要な投資」であるという前提 Webサイトは短期的な経費削減ではなく、中長期的に価値を生む資産形成です。助成がない場合でも事業効果が見込める設計であることが大切です。
- 施策の優先順位を明確にした段階的実行 助成対象外の施策(例:SNS広告・多言語化・採用ページの強化など)は段階的に導入することで、無理のない資金設計が可能になります。
- 助成制度ごとの制約に引きずられない自由な構想 制度によっては「導入できるツールや事業目的の範囲」が限定されることもあります。そうした枠に合わせるのではなく、自社の理想のWeb活用像を軸に計画することが肝心です。
Webaxisではこのような“補助金に左右されない視点”を重視し、企業の未来に価値を残す制作プランをご提案しています。
💡 補助金は“選択肢を広げるツール”であり、“進むべき道”を決めるものではありません。
成果にこだわるのであれば、まずはゴールから逆算した戦略設計を描くことが重要です。

まとめ|補助金・助成金は“使いこなす”視点で
ホームページ制作に補助金・助成金を活用することは、経営者や広報担当者にとって非常に魅力的な選択肢のひとつです。しかし、制度の存在に振り回されてしまうと、本来得られるはずの成果や本質的な価値が薄れてしまうことも少なくありません。
ここでは改めて、補助制度を賢く「使いこなす」ための視点を2つの観点からまとめます。
制度に振り回されず、目的から逆算する計画を
補助金や助成金の詳細を調べ始めると、「この制度に当てはめるために何をすべきか?」という視点になりがちです。しかしそれでは、戦略が制度に“従属”してしまい、必要な要素を削る、見せかけの構成になる、といったリスクを招きかねません。
本当に必要なのは、以下のような目的起点の逆算的な設計です。
- まず「成果を出すための理想のWebサイト像」を描く (例:集客に強い導線設計/採用力強化のコンテンツ構成/SNSとの一体運用)
- その理想を実現するために「どの施策が補助対象になるか」を検討する 制度はその手段にすぎないため、必要に応じて段階的な導入や別手段の検討も含めて柔軟に対応することが重要です。
制度の変化や予算の採択に一喜一憂せず、「自社にとって必要な施策は何か」という軸を持つことで、結果的に納得度と成果の高いWeb施策が実現できます。
「今、ホームページを作る意味」を言語化する
補助金の申請や計画書をつくる段階では、**「なぜこのタイミングでホームページを制作するのか」**という理由を明確にしておくことが欠かせません。これは採択のためだけでなく、経営判断や社内合意形成の上でも非常に重要です。
たとえば:
- 「これまでの営業スタイルを変える必要性を感じており、オンラインでの情報発信を強化したい」
- 「採用が厳しくなっており、若手人材に響く企業サイトに刷新したい」
- 「福岡エリアでの認知拡大に向け、検索からの集客を増やしたい」
こうした自社の現状・課題・目的を言語化することで、補助金の活用は“書類上の施策”から“経営戦略の一部”へと昇華します。
また、目的の明確化はブレない情報設計やデザイン方針の軸にもなり、制作全体の品質と成果を高めることにつながります。
💡 補助金はゴールではなく、「必要な投資を後押しするための制度」です。
制度の有無に関わらず、自社の未来につながる判断をすることこそが最も重要です。
▷ 福岡でホームページ制作を検討するなら、費用相場と見積の“見極め力”がカギに
補助金や助成金を活用してホームページを制作する際、多くの方が気になるのが「実際の費用はどのくらいかかるのか?」という点です。とくに福岡では、制作会社の得意分野や提供スタイルによって料金体系が大きく異なり、同じ要望でも数十万円単位で見積もりに差が出ることも珍しくありません。
さらに、サブスク型と買い切り型、初期費用と運用費用、補助金を使うか否かなど、複雑に絡み合う要素が判断を難しくさせています。
Webaxisでは、福岡の企業が成果につながるホームページを適正価格で実現するために、費用の“内訳”や“相場感”、そして“本当に必要な投資とは何か”を正しく理解することがスタート地点だと考えています。
以下の記事では、
- 福岡における制作料金の相場感
- 各制作モデルの費用構成
- 見積もりに潜む“隠れコスト”の注意点
- 補助金や助成金活用時の費用設計
といったポイントを、2025年の最新事情をもとに解説しています。
補助金ありきではなく、費用対効果の高い制作を実現するために、まずは以下のページをご覧ください。
👉 福岡のホームページ制作費用相場と見積もりのポイント【2025年版】
費用感を正しく把握し、「安いから決めた」ではなく「納得して選ぶ」ための視点が得られる1本です。
福岡の企業が成果を出すためには、ホームページとSNSを個別の施策ではなく、ブランド体験全体を設計する起点として捉える視点が欠かせません。本記事では、Webaxisの知見と事例をもとに、ホームページ制作からSNS活用、戦略設計、KPI運用までを一貫した“つながり”として設計する方法を解説しています。全記事を通じて、地域で選ばれるブランドの土台を共に築く一助となれば幸いです。