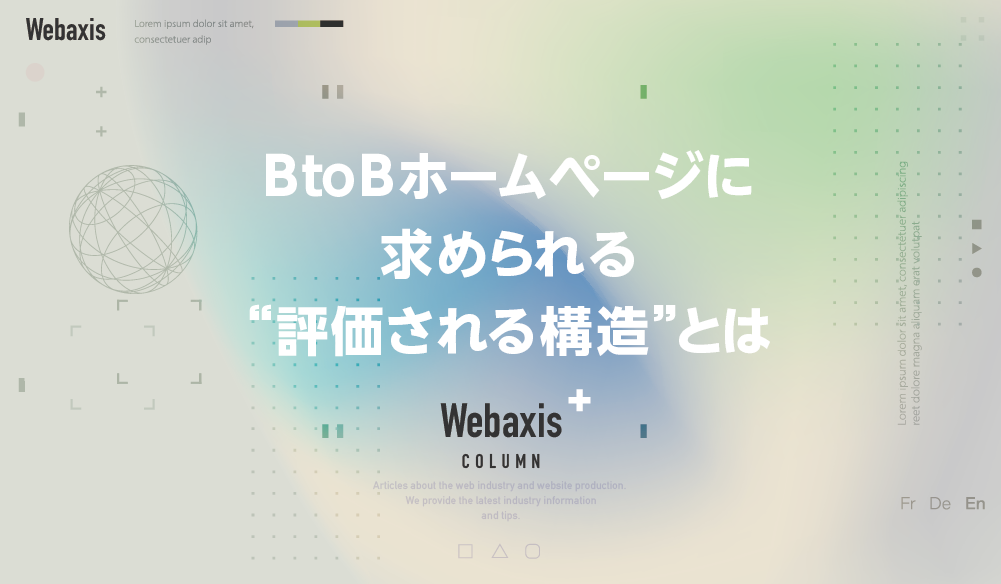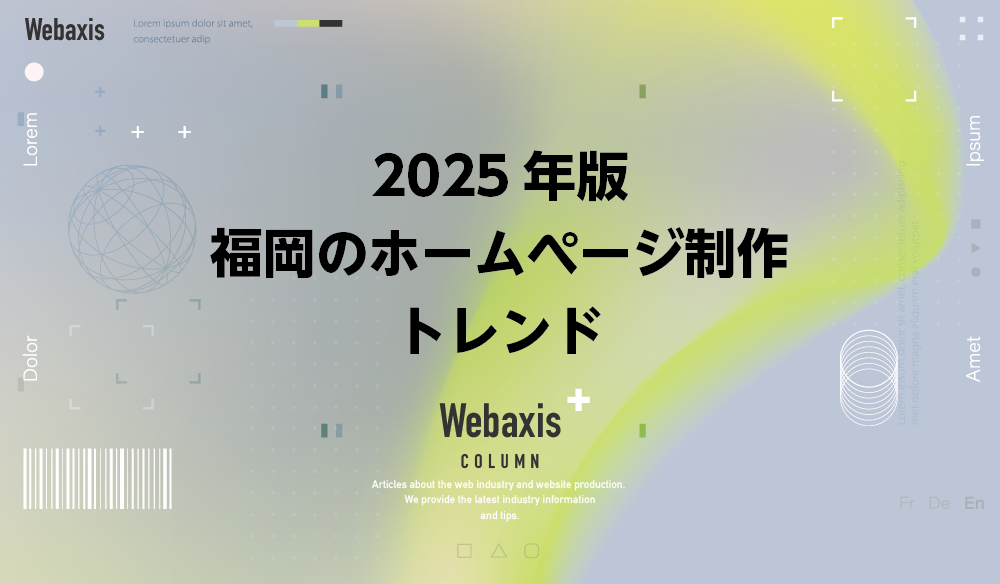BtoB SNS運用とブランド検索の関係性を可視化する
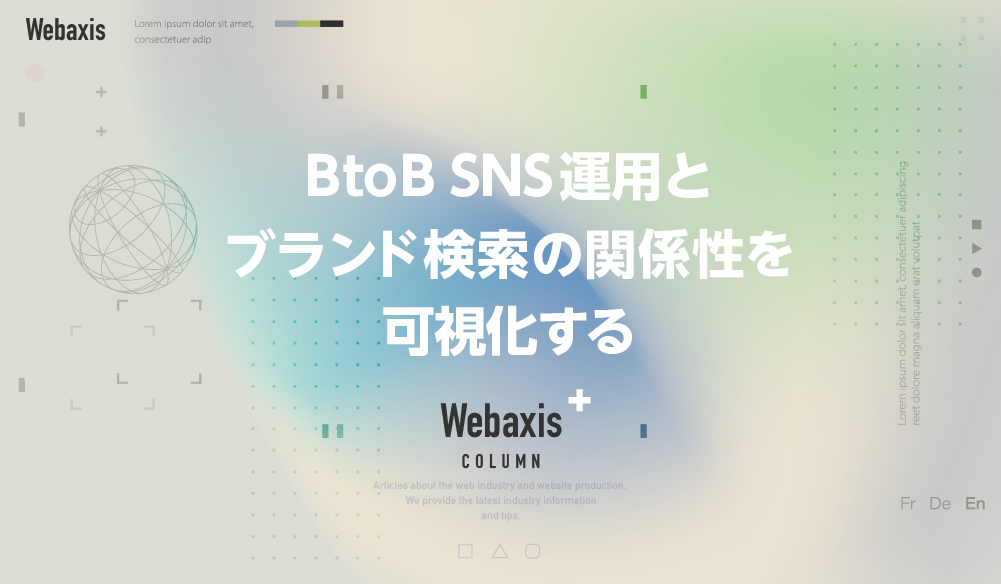
BtoBにおけるSNS運用は、これまで「拡散性が弱い」「CVに直結しない」と見なされがちでした。
しかし、近年のGoogle評価アルゴリズムでは「ブランド名で検索されているか(=ナビゲーショナルクエリ)」が、企業の信頼性やオーソリティとして強く評価される指標になっており、状況は一変しています。
実際に、Twitter(X)やLinkedIn、noteなどで発信を続けている企業ほど、「ブランド名+サービス名」「ブランド名+評判」といった検索が増加し、SEO外部評価の土台が強化される傾向にあります。
このページでは、Webaxisが実務で支援してきた事例をもとに、BtoBにおけるSNS運用がどのように指名検索を生み、SEO外部対策として機能するかを徹底的に解説します。
単なる発信ではなく、“検索される前提”で設計するBtoB SNS活用戦略の構築方法を紐解いていきます。
目次
なぜBtoBでもSNSが“指名検索”を増やすのか?
SNS運用は一見、BtoCに向いている施策のように思われがちですが、実はBtoBにこそ“検索行動を促す”メディアとしての価値があります。
商談や検討に至る前段階で、「社名を聞いた」「投稿を見かけた」「誰かが紹介していた」──このような情報接触があると、多くのビジネスパーソンはまず社名やサービス名をGoogleで検索します。
ここでは、BtoBにおけるSNSの本質的な役割と、その先にあるブランド検索→SEO外部評価へのつながりを明らかにします。
BtoBにおけるSNSは“ナーチャリングの最初の接点”
BtoBでは、見込み顧客の検討期間が長く、直接的なCVよりも継続的な情報接触(ナーチャリング)が重視されます。
その中で、SNSは営業接点よりも早い段階で、「知っている」「見かけたことがある」という最初の認知と印象形成の役割を担います。
たとえば、
- 自社社員のnote記事が拡散される
- LinkedInで登壇報告が共有される
- Xで事例コンテンツが流れてくる
といった形で、“検索に至る種”がSNS上にまかれます。
この接触が「気になる会社だな」という認知に変わった瞬間、ユーザーは指名検索(ナビゲーショナルクエリ)へと進むのです。
“信頼できそうな会社”と認識されたとき人は検索する
BtoBユーザーは衝動的にサービスを選ぶことはありません。
むしろ「この会社、信頼できそうか?」「業界的にちゃんとしてるか?」といった信頼前提の情報を自主的に探す傾向があります。
SNS上で何度も目にする会社があった場合、ユーザーは以下のような検索を行います:
- 「◯◯株式会社 評判」
- 「◯◯ SaaS機能 比較」
- 「◯◯ 導入事例」
- 「◯◯社長 note」
このようなブランド名を含む検索行動(指名検索)が増えること自体が、Googleにとってはその企業が“調べる価値のある存在”である証拠となり、SEO外部評価として認識されます。
ナビゲーショナルクエリがSEO評価に変わるまでの構造
Googleは、ユーザーの検索行動を次のように分類しています。
| クエリ種別 | 意図 |
|---|---|
| トランザクショナル | 購入・申込・行動 |
| インフォメーショナル | 調査・比較・検討 |
| ナビゲーショナル | ブランドやサイト名での直接検索 |
この中でも、ナビゲーショナルクエリの増加は「ブランド認知と信頼の蓄積」を意味し、SEOにおいては極めて高い外部評価シグナルとして機能します。
BtoB SNS運用がこのナビゲーショナルクエリを増やすことに寄与すれば、それはSEOにおける“リンク以外の評価資産”=サイテーションとして、検索順位の向上に影響を与えるのです。
SNS投稿→検索→信頼の強化へとつながる導線設計
SNSでの投稿が指名検索につながり、さらにWebサイトでの信頼醸成につながる――この一連の流れは、BtoB企業にとって“ブランド信頼を検索評価に転化する”ための導線です。
しかし、これはただ投稿をするだけでは成立せず、「検索を誘発する投稿設計」と「信頼の受け皿となるWeb設計」の連動が必須です。
このセクションでは、SNS→検索→信頼の強化という文脈循環を、具体的な設計視点から解説します。
話題のフックより“再検索される専門性”が重要
BtoCでは感情や共感が拡散の起点になりますが、BtoBでは専門性・実績・独自視点が投稿に含まれていることが、検索につながる鍵です。
例
- ❌「新しいサービスをリリースしました!」
- ✅「SaaS導入で“人事評価制度を再設計”した事例を公開しました」
- ✅「製造業のリードタイム短縮に効くCRM活用方法(製造業×CRM)」
このように、「ユーザーが続きを知りたくなる切り口」を持った投稿が、再検索を誘発します。
Webaxisでは、SNSを単なる露出手段ではなく、「検索文脈を設計する前段階」と位置づけています。
SNSからブランド名で再検索される投稿の作り方
ブランド名で検索されるためには、投稿文の中に自然な形でブランド名が登場し、印象に残ることが大切です。
「どこの会社が発信しているか」が不明な投稿は、検索にもつながりません。
ポイント
- 投稿文に「〇〇株式会社」「〇〇の導入支援をしている〇〇です」などを明記
- URLリンクではなく、社名検索につながる言い回しを意識(例:「詳しくは“〇〇株式会社”で検索」)
- ハッシュタグで社名・プロダクト名を活用(例:#Webaxis #SEO外部対策)
このように、投稿設計そのものが“検索される前提の設計”になっていることが重要です。
認知→検索→E-E-A-TへつなげるSNSとWebの連動設計
SNSでの接触からブランド名検索へと至ったユーザーは、必ずWeb上で“答え合わせ”をしようとします。
そのとき、WebサイトがE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)に基づく設計になっていなければ、せっかくの検索は評価にもCVにもつながりません。
Webaxisが実践している連動設計
| フェーズ | 設計内容 |
|---|---|
| SNS投稿 | 検索を促す専門コンテンツの発信・ブランド名明記 |
| 検索時 | ブランド名で上位表示されるWeb構造の整備(指名検索対策) |
| 訪問時 | 専門性・実績・事例・発信履歴を網羅した構成で信頼を醸成 |
このように、SNSで得た関心を“検索→評価→信頼→CV”に昇華させる導線構築が、BtoBにおけるサイテーション戦略の根幹です。
SNS運用でBtoB指名検索を誘発するコンテンツ設計
SNSを通じてBtoBで指名検索を誘発するためには、「何をどう発信するか」が極めて重要です。
BtoCのようなUGC(ユーザー生成コンテンツ)ではなく、企業自身の専門性を活かした“信頼性の高い情報コンテンツ”をSNSから展開し、それを検索につなげる設計が求められます。
このセクションでは、BtoBにおいて有効なSNSコンテンツ設計の具体例を解説します。
UGCではなく“専門性コンテンツUGC”をどう誘導するか
BtoBでは「ユーザーに話題化してもらうUGC」よりも、業界内・取引先・社員による“信頼性の高い言及”が評価されやすい傾向にあります。
SNS上でも、ユーザーが引用・コメントしやすい“専門性ベースの発信”を設計することで、ナチュラルなサイテーション(ブランド言及)が発生しやすくなります。
たとえば:
- 有識者によるセミナーレポートの共有
- 共催イベントの開催報告
- 業界トピックに対する自社の考察記事
これらは「引用・引用元としてのブランド名」が明示されやすく、検索行動につながる“信頼性コンテンツ型UGC”として有効です。
投稿にブランド名が自然に含まれるネーミング設計
ブランド名が検索されるためには、投稿や発信において“自然に社名が登場する構造”をつくることが鍵になります。
これには、以下のような“語られやすいブランド名の設計”が有効です。
- 長い会社名は短縮形・略称を明示(例:株式会社〇〇 → 〇〇社)
- サービス名・ツール名に社名要素を含める(例:「Webaxis Tracker」など)
- 自社投稿だけでなく、共催・タイアップ時にも「社名が見える」形にする
こうした工夫により、検索エンジンがブランド名と文脈を結びつけやすくなり、SEO外部評価に変換される確率が高まります。
事例・登壇・イベント発信が再検索を生む
BtoBでは“リアルな接触”が信頼につながる傾向があるため、セミナー・展示会・講演・記事寄稿などの露出情報をSNSで発信することは、再検索を誘発する強力な施策です。
具体例
- 「◯◯イベントに弊社CMOが登壇します。#〇〇イベント #〇〇株式会社」
- 「○○業界向けCRM導入事例をnoteで公開しました」
- 「〇〇社との共催セミナー、参加者200名超。資料はこちら」
こうした投稿は、投稿→検索→ホームページ訪問→CVというBtoBらしい導線を自然に作り出します。
特に検索エンジンにとっては、「社名での検索」「登壇内容の言及」「他サイトからの自然リンク」など、強いサイテーション評価指標として蓄積されていきます。
Webaxisが実践するBtoB SNS×SEO戦略のポイント
Webaxisでは、SNS運用を「ブランドの人となりを伝える場」として捉えると同時に、“検索されるブランドを設計する外部対策”として戦略的に活用しています。
BtoB領域においては、CV獲得だけでなく、指名検索→信頼→SEO外部評価という中長期的な循環を意図して、SNSとWebの文脈を設計しています。
このセクションでは、私たちが支援で実践している指名検索を生むためのSNS×SEO戦略の3つの具体ポイントをご紹介します。
指名検索を目的としたSNS KPIと投稿指針の再定義
SNS運用のKPIが「いいね数」「クリック率」だけに留まっていると、SEO的な効果は期待できません。
Webaxisでは、「ブランド名検索数の増加」「検索行動に至る接触投稿の量」をSNS運用の評価指標として再設計します。
具体的な再定義の例
- 指名検索ワードのSearch Console監視 → SNS運用と相関を確認
- SNS投稿に含まれるブランド名の登場頻度を計測
- ブランド名で検索した際に上位表示させるページの整備
これにより、SNS運用を“SEO外部評価のための仕込みフェーズ”として可視化・改善することが可能になります。
検索文脈とWeb文脈の統合で“検索→信頼”を最適化
SNSで興味を持ち検索されたユーザーが、Webサイトに訪れた瞬間、“一致した文脈”で情報に触れられるかどうかが信頼形成の鍵になります。
そのため、SNSとWebは「切り離された施策」ではなく、共通の設計思想でつなげておく必要があります。
Webaxisが行っている統合施策の例
| SNS投稿 | Web受け皿 |
|---|---|
| 導入事例の告知投稿 | 事例ページに詳細記事と顧客インタビュー掲載 |
| 登壇情報のSNSシェア | サイト内に「登壇・メディア掲載一覧」ページ設置 |
| 社員noteの拡散 | noteから自社サービスLPへ内部リンク誘導 |
このように、検索行動の背景にある“文脈”をWebで正しく受け止める構造を整えておくことで、ブランド評価は飛躍的に高まります。
“語られ方”の再設計でナビゲーショナル評価を最大化
Googleが企業を評価する際、重要視しているのが“どのように語られているか”=コンテキスト(文脈)です。
つまり、単なる社名の出現回数よりも、「どんな投稿の中で」「どんな専門性と共に」「誰に語られているか」が問われます。
そのために必要なのが
- 「〇〇といえばこの会社」という語られ方(タグライン・切り口)の設計
- 投稿テンプレートや広報方針の整備(例:「〇〇の専門家として発信」)
- インフルエンサーや業界パートナーとの共同投稿の設計
このような“文脈評価を前提とした語られ方のデザイン”が、ナビゲーショナルクエリの質を高め、SEO外部評価へと直結します。
まとめ|CVだけで測れない“指名検索設計”がBtoB SEOの鍵に
BtoBマーケティングにおいて、SNSは「直接CVにつながりにくい施策」と見られることも少なくありません。
しかし実際には、SNSによる接触は指名検索という強力な評価シグナルを生み出し、SEO外部対策として機能する“検索設計の起点”となります。
Webaxisでは、SNSを単なる発信チャネルではなく、「検索される企業ブランド」を育てる設計装置として位置づけ、検索行動・評価獲得・信頼醸成のすべてを接続する支援を行っています。
ブランド名で検索されるということの意味
「ブランド名で検索される」という行為は、ユーザーがすでにその企業を“認知し、信頼に値するか確認したいと感じている”証拠です。
この検索が繰り返されれば、Googleはそれを企業の人気・信頼・専門性のシグナルとして捉え、ナビゲーショナルクエリの多寡がSEO外部評価に直結していきます。
つまり、SNSでの信頼構築→検索→訪問という流れは、SEOにおけるサイテーション評価の土台そのものなのです。
BtoBマーケにおける「検索設計としてのSNS運用」へ
SNSは「いいね」や「フォロワー数」ではなく、「検索を生み出したかどうか」で成果を測るべきフェーズに入っています。
BtoBにおいては特に、検索されること=選ばれることであり、それを促すSNSコンテンツ設計・Web連携・ナビゲーショナル強化は、企業ブランドの資産化にも直結します。
SNSとWeb、発信と信頼、文脈と検索――これらを“循環する仕組み”として設計することが、これからのBtoB SEOに不可欠な外部対策戦略です。