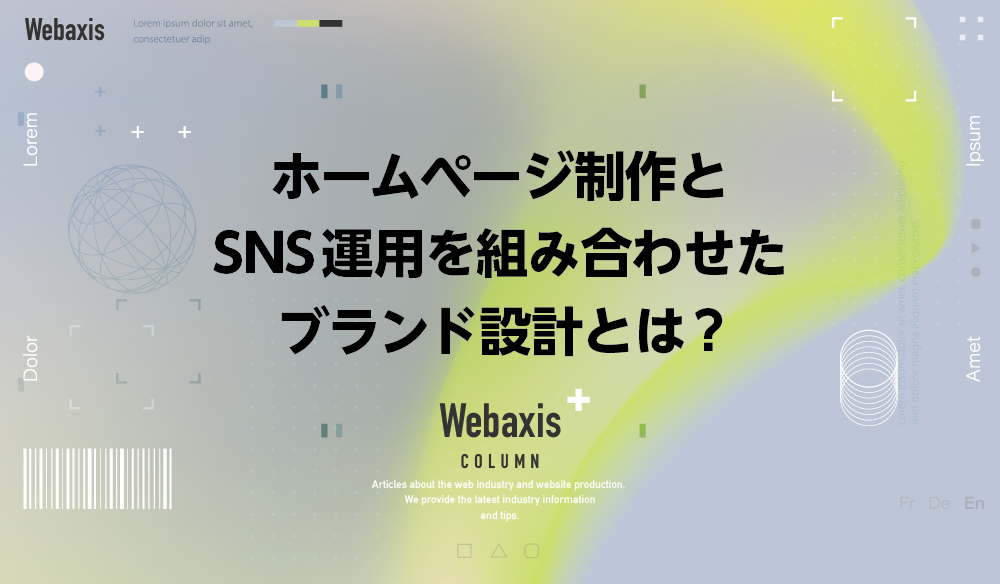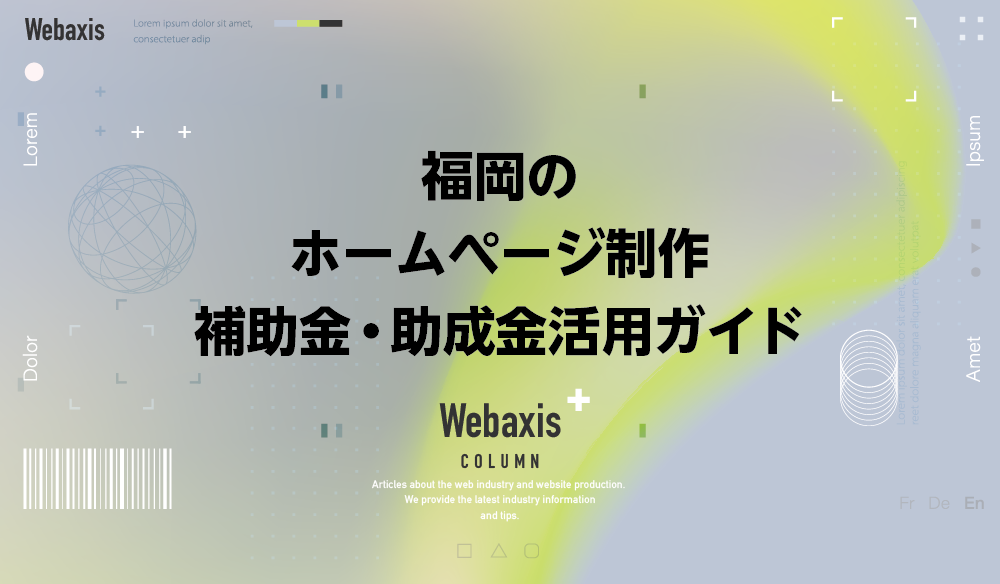初めてのホームページ制作で押さえるべき10のポイント
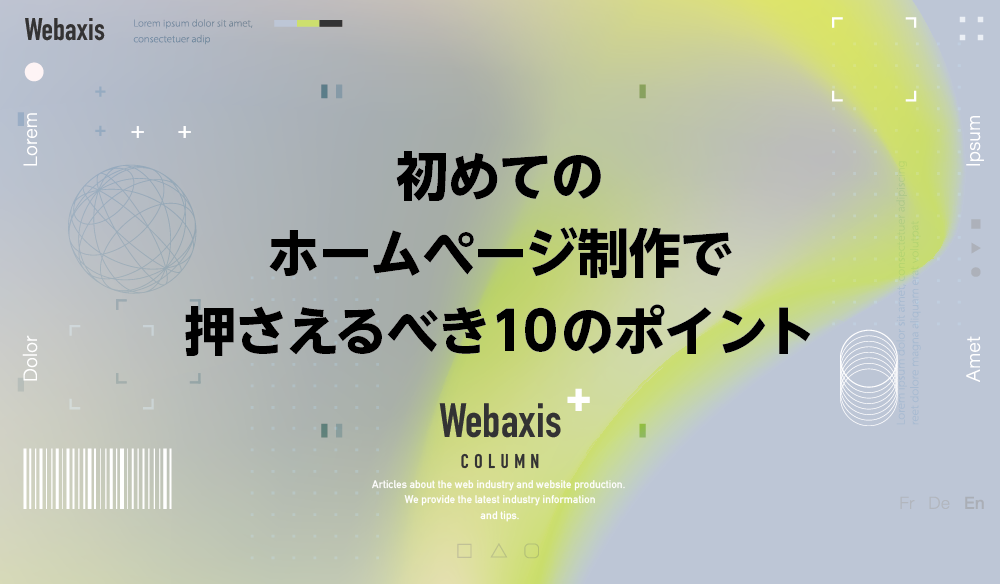
はじめに|初めてのホームページ制作がなぜ“今”重要なのか
福岡の中小企業やスタートアップにとって、ホームページは単なる会社案内の役割を超え、営業・採用・ブランディングの中心的な存在になっています。特に2025年6月のGoogleコアアップデート以降、検索評価の基準は大きく変化しました。これまで以上に「ユーザーファースト」「文脈整合性」「E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)」が重視され、見た目だけでは評価されない時代です。
その結果、目的やターゲットが不明確なまま制作されたサイトは検索順位を下げ、一方で、ユーザーの課題解決や信頼性のある情報を提供するサイトは評価を高めています。本記事では、初めてホームページ制作に取り組む企業が、Googleコアアップデート後の評価軸に沿って成果を上げるための10のポイントを、現場での実務経験と最新のSEO知見に基づいて解説します。
目次
目的設定とKPI設計|制作前にやるべき最初のステップ
ホームページ制作において最初に取り組むべきは、サイトの目的と達成基準を明確化することです。この段階で曖昧なまま進めると、公開後に「問い合わせが来ない」「アクセスが伸びない」といった問題が起きます。目的は1つに限定する必要はなく、複数設定して優先順位を決めることが大切です。さらに、その目的を数値で評価するためのKPI(重要業績評価指標)を設計し、GA4やSearch Consoleなどで測定可能な形に落とし込むことで、改善サイクルを確実に回せます。
ホームページ制作の目的を明確化する方法
目的は企業の事業戦略や課題から逆算して設定します。例としては、新規顧客の獲得、採用活動の強化、既存顧客への情報発信、ブランド認知の向上などが挙げられます。目的ごとに求める成果やターゲット層が異なるため、制作時点からサイト構造やコンテンツの優先度を調整することが必要です。
KPI(重要業績評価指標)の設定と追跡方法
KPIは「達成できそうな数字」ではなく、「達成すべき数字」に設定します。
例として、新規顧客獲得なら「月間問い合わせ数30件」、採用活動なら「月間応募数10件」、ブランド認知なら「ブランド名検索数20%増加」などが考えられます。これらをGA4でのコンバージョン設定やSearch Consoleのクエリ分析と紐付けることで、定期的な追跡と改善が可能になります。
| 目的 | KPI例 | 測定ツール |
|---|---|---|
| 新規顧客獲得 | 月間問い合わせ数30件 | GA4(コンバージョン設定) |
| 採用活動 | 月間応募数10件 | エントリーフォーム解析 |
| ブランド認知 | ブランド名検索数20%増加 | Search Console |
ターゲットユーザー分析|ユーザーファースト設計の基盤
Googleコアアップデート2025では、検索評価において「ユーザー意図の把握」と「文脈整合性」がこれまで以上に重視されています。つまり、単にキーワードを盛り込んだだけのページでは評価されず、ユーザーが抱える課題や求める情報に正確に応えることが不可欠です。そのための出発点がターゲットユーザー分析です。企業規模や業種に関わらず、まずは「誰に」「何を」「どのように」伝えるのかを明確にする必要があります。
ペルソナ設定の手順と実務例
ペルソナとは、サイトの典型的な利用者像を詳細に描いた架空の人物モデルです。年齢、性別、役職、課題、行動特性、情報収集経路まで具体的に設定します。例えば福岡の製造業経営者をターゲットとする場合は、次のようになります。
- 年齢:45歳
- 役職:代表取締役
- 課題:新規取引先の開拓、慢性的な採用難
- 行動特性:Google検索で調査、業界展示会に参加、業界誌購読
このように人物像を描くことで、ページ構成・導線設計・コンテンツの言葉遣いまで統一感を持たせられます。
Googleコアアップデート2025が求めるユーザー意図の把握方法
ユーザー意図は、Search ConsoleやGoogleキーワードプランナーなどのツールで可視化できます。重要なのは、単一のメインキーワードだけでなく、それに関連する複合キーワードやサジェストキーワードも含めて分析することです。例えば「ホームページ制作」というキーワードであれば、「ホームページ制作 事例」「ホームページ制作 費用」「ホームページ制作 流れ」などの関連ワードを調べ、それぞれの背景にあるニーズを読み取ります。
「費用」と検索している場合は価格や予算感に関する情報を、「流れ」で検索している場合は制作プロセスやスケジュール感を知りたい可能性が高いです。このように検索語の裏側にある意図を読み解き、それに応じたコンテンツを設計することで、検索エンジンからの評価とユーザー満足度を同時に高められます。

コンテンツ戦略と情報設計|SEOとUXを両立させる構成
制作の成否を左右するのは「どのような情報を、どの順番で、どの形式でユーザーに届けるか」です。Googleコアアップデート以降は、情報の網羅性だけでなく、その情報が検索意図に沿って整理されているかどうかが評価のポイントになっています。SEOの視点からは、適切なキーワード配置や内部リンク設計が欠かせませんが、同時にユーザーがストレスなく目的の情報に辿り着けるUX設計も必要です。このバランスを取ることで、検索順位の向上とコンバージョン率の改善を同時に実現できます。
サイトマップ作成の基本と注意点
サイトマップは、サイト全体の情報構造を可視化する設計図です。大きく分けて「HTMLサイトマップ」と「XMLサイトマップ」があり、前者はユーザー向け、後者は検索エンジン向けです。構築の際には以下を意識します。
- 階層構造を3階層以内に収める(トップ → カテゴリ → 詳細)
- カテゴリ間の関連性を明確にする(内部リンクで補強)
- 不要なページを含めない(SEO評価の分散を防ぐ)
特にXMLサイトマップはGoogle Search Consoleに登録しておくことで、クロール効率を高め、インデックス速度を向上させられます。
キーワード選定と検索意図の多層構造分析
コンテンツ制作では、1つのキーワードだけに依存せず、「ビッグキーワード」「ミドルキーワード」「ロングテールキーワード」の3階層で設計します。
| キーワード種別 | 例 | 特徴 |
|---|---|---|
| ビッグキーワード | ホームページ制作 | 検索ボリューム大・競合多い |
| ミドルキーワード | ホームページ制作 流れ | ニーズ特定・競合中程度 |
| ロングテールキーワード | ホームページ制作 流れ 初心者向け | 成約率高・競合少ない |
検索意図は「情報収集」「比較検討」「購入・契約」の3段階に分かれます。これらの意図を段階ごとにカバーすることで、ユーザーを自然にコンバージョンへ誘導できます。
E-E-A-Tを意識したコンテンツ設計
Googleは、専門性(Expertise)、権威性(Authoritativeness)、信頼性(Trustworthiness)、経験(Experience)を総合的に評価します。コンテンツ内に以下を盛り込むとE-E-A-Tが強化されます。
- 経験(Experience):現場での事例や体験談の共有
- 専門性(Expertise):資格保持者や専門家監修の記載
- 権威性(Authoritativeness):業界団体や大手メディアからの引用
- 信頼性(Trustworthiness):出典明記、情報の更新日表示
これらを意識して設計することで、単なる情報の寄せ集めではない「評価されるコンテンツ」に仕上がります。
デザインとUI/UX設計|ブランド体験を強化する
ホームページは企業の「顔」として、訪問者に与える第一印象を決定づけます。見た目の美しさだけでなく、ユーザーが迷わず目的を達成できる設計が不可欠です。Googleは直帰率や滞在時間などの行動データも評価に反映しており、UI/UX(ユーザーインターフェース/ユーザー体験)の質はSEOにも直結します。特に福岡のような競合が多いエリアでは、第一印象と操作性の両方を高めることで差別化が可能です。
ファーストビューで信頼を得るデザイン要素
ファーストビューは、ページを開いた瞬間に見える範囲のことです。この瞬間に「このサイトは信頼できる」と思わせられるかが、離脱率を左右します。
- キャッチコピー:誰に何を提供しているかを端的に示す
- ブランドカラーとフォント:統一感を持たせて印象を強化
- CTA(行動喚起)ボタン:目立つ位置と色で設置
- 視線誘導:重要情報に視線を集めるレイアウト設計
例えば、ファーストビュー内に実績や受賞歴を掲載すると、信頼性が一気に高まります。
UI/UX改善が直帰率・滞在時間に与える影響
UI/UXの改善は、訪問者の行動指標に直結します。直帰率の高いページは、目的の情報にたどり着きにくい構造や視覚的なノイズが原因の場合が多いです。改善方法としては以下が挙げられます。
- ナビゲーションの明確化:メニュー項目を簡潔にし、階層を浅くする
- レスポンシブデザイン:スマホ・タブレットでも快適に閲覧可能に
- フォーム最適化:入力項目を最小限にし、離脱を防ぐ
- ページ速度向上:画像圧縮や不要スクリプト削除で読み込みを短縮
こうした改善は、滞在時間を延ばし、検索評価を高める効果も期待できます。
モバイルファーストとレスポンシブ対応|スマホ時代の必須条件
スマートフォンからのアクセスが全体の70%以上を占める現在、モバイルでの閲覧体験はホームページの成果を左右します。Googleは「モバイルファーストインデックス」を採用しており、スマホ版の評価がそのまま検索順位に反映されます。福岡のような都市部では、外出先や移動中に情報収集を行うユーザーが多いため、モバイルでの見やすさ・使いやすさがコンバージョン率を左右します。
Googleのモバイルインデックスの仕組み
スマートフォンからのアクセスは、今や全体の7割以上を占めています。Googleが採用しているモバイルファーストインデックスでは、スマホ版ページの構造や表示内容がそのまま検索順位の評価基準となるため、PC版だけを整えても成果は望めません。特に福岡のような都市部では、移動中や外出先で情報を探すユーザーが多く、スマホ表示の質がコンバージョン率に直結します。重要な情報は必ずモバイル版にも反映させ、テキストや画像の抜け漏れがないようにしましょう。また、Google公式のモバイル対応テストを活用し、定期的に表示や操作性をチェックすることも欠かせません。
モバイルUX改善のチェックポイント
モバイルでのユーザー体験を高めるためには、指での操作を前提とした設計が必要です。ボタンやリンクはタップしやすいサイズを確保し、入力フォームは数字欄で数字キーボードが自動表示されるように設定します。さらに、最初のスクロールで目的の情報に到達できるレイアウトを心がけ、ポップアップや煩雑な広告で視界を妨げないことも重要です。こうした配慮が、滞在時間の延長や成約率の向上につながり、結果的にSEO評価にも好影響を与えます。
SEO内部施策の基本|構造化データと内部リンク戦略
SEO内部施策は、検索エンジンがサイトを正しく理解し、評価を高めるための基礎となります。特に内部リンクと構造化データは、コンテンツの関連性や専門性を伝えるうえで重要な役割を果たします。適切な設計と実装は、検索順位だけでなく、ユーザーの回遊性や滞在時間の向上にもつながります。
内部リンクとクラスター構造の設計
内部リンクは、Googleがサイト内の情報を理解するための道筋です。トップページからカテゴリーページ、さらに個別記事へとつながる階層構造を整備し、関連性の高いコンテンツ同士を相互にリンクさせることで、検索エンジンにテーマの専門性を示すことができます。特にトピッククラスター型の構造は、1つの主要テーマを中心に複数の記事を束ねる形となり、特定キーワードでの上位表示に有効です。リンクテキストには内容を正しく示す言葉を使い、読者にも検索エンジンにも分かりやすい設計を心がけましょう。
構造化データ(Schema.org)による検索結果最適化
構造化データは、検索結果の見た目とクリック率を向上させる重要な要素です。Schema.orgを活用して、FAQ、レビュー、パンくずリストなどの情報をマークアップすることで、リッチリザルトとして表示される可能性が高まります。これによりCTRが改善され、間接的に順位向上につながることもあります。導入時には、Googleの構造化データテストツールでエラーがないかを確認し、検索意図と一致した情報を正しく実装することが重要です。

SEO外部施策とブランドの信頼性向上
SEO外部施策は、検索エンジン外からの評価を高め、ブランドの信頼性を強化する重要な手段です。被リンクやSNSでの言及は、第三者からの評価としてGoogleに認識され、E-E-A-Tの「権威性」と「信頼性」の要素を後押しします。特に近年は、関連性の高い媒体やインフルエンサーとの連携が成果につながりやすくなっています。
被リンク獲得戦略とブランド言及の増やし方
高品質な被リンクは、単なるSEO効果だけでなく、ターゲットユーザーへの露出を増やします。業界メディアへの寄稿、共催イベント、専門家インタビューなどは有効な方法です。また、ブランド名やサービス名が自然に言及されるコンテンツを増やすことで、リンクがなくても評価が高まるケースがあります。
SNSとホームページの相互連携による認知拡大
ホームページへの流入経路としてだけでなく、SNSはブランドの世界観やストーリーを伝える場でもあります。SNSで得た反応をもとに、ホームページのコンテンツを改善する循環を作ると効果的です。リンクの設置だけでなく、投稿内でのストーリーや事例紹介を通じて、自然な誘導を行うことが重要です。
セキュリティとサイトパフォーマンス|信頼性とUXの裏側
ホームページはデザインやコンテンツだけでなく、ユーザーが安心して利用できる環境の提供が重要です。セキュリティ対策が不十分であれば、ユーザー離れやブランドイメージ低下の原因となり、検索エンジンからの評価にも悪影響を及ぼします。また、表示速度やパフォーマンスの最適化は、ユーザー体験の質を左右する大きな要素です。ここでは、セキュリティとパフォーマンス向上のための実践的な方法を解説します。
SSL/TLS対応とHTTPS化の重要性
SSL/TLSによる暗号化通信は、ユーザーの個人情報を守るための必須条件です。HTTPS化されたサイトは、ブラウザで「安全」と表示されるほか、Googleのランキング要因としてもプラス評価を受けます。証明書の定期更新や自動更新設定を行い、常に最新の状態を保ちましょう。
Core Web Vitals最適化の実践ポイント
Core Web Vitalsは、ページの表示速度、インタラクションの応答性、レイアウトの安定性を測定する指標です。これらの数値を改善するためには、画像や動画の軽量化、不要なスクリプトの削除、キャッシュ設定の最適化などが有効です。Google Search ConsoleやPageSpeed Insightsを活用し、定期的に数値を確認・改善することが重要です。
公開後の分析と改善サイクル|PDCAで成長するサイト運用
ホームページは公開して終わりではありません。むしろ公開後の分析と改善こそが、長期的な成果を左右します。Googleコアアップデートなど外部要因によって順位や流入が変動するため、定期的なモニタリングと改善が必要です。PDCA(Plan→Do→Check→Act)のサイクルを習慣化することで、常に最新の検索評価基準やユーザー行動に適応したサイト運用が可能になります。
GA4とヒートマップツールの活用方法(Clarity・Hotjar等)
Googleアナリティクス4では、訪問者の流入経路やコンバージョン率を把握できます。さらに、ClarityやHotjarといったヒートマップツールを併用すると、クリック率やスクロールの深さ、離脱ポイントなど、ユーザー行動を可視化できます。これらのデータは、改善の優先順位を決める際の重要な判断材料になります。
Googleコアアップデートに対応する継続改善の手順
アップデート後に順位が変動した場合は、該当ページの検索意図との整合性やコンテンツ品質を再確認します。競合分析を行い、情報不足や古いデータの更新、見出し構造の見直しなどを行うことで、評価の回復や向上が期待できます。加えて、改善後は必ず計測期間を設け、施策の効果を定量的に検証することが重要です。
制作パートナーの選び方|福岡で信頼できる制作会社の基準
パートナー選びは、ホームページ制作の成否を大きく左右します。福岡には多くの制作会社がありますが、単にデザインが優れているだけでなく、戦略設計や運用改善まで一貫して対応できる企業を選ぶことが重要です。また、制作後のサポート体制や改善提案の有無も、長期的な成果に直結します。
制作会社選びのチェックリスト
制作会社を選ぶ際には、実績の豊富さ、担当者のコミュニケーション力、SEOやマーケティングの知見、納期遵守力などを確認します。また、契約前に制作フローや成果物の範囲を明確にすることで、後々のトラブルを防げます。
見積もり比較と契約時の注意点
見積もりは金額だけでなく、提供内容と成果物の範囲を詳細に比較します。特に保守費用や追加開発費用など、長期的なコストも含めて判断することが大切です。契約書には修正回数や納品形態、著作権の帰属など重要事項を明記しましょう。
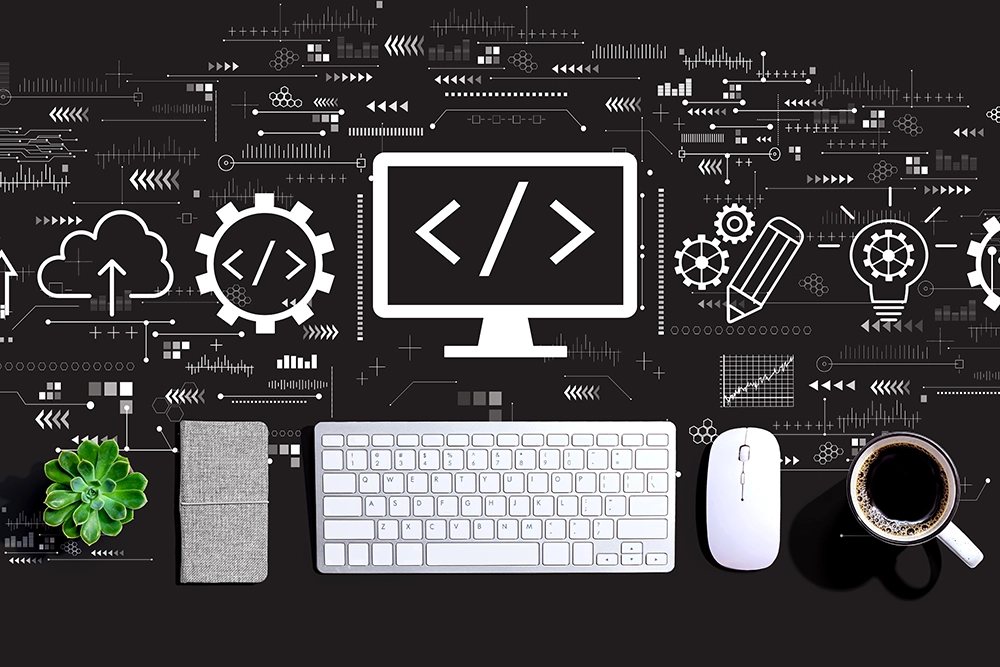
まとめ|初めてのホームページ制作を成功に導くために
初めてのホームページ制作は、多くの意思決定と準備を必要とするプロジェクトです。本記事で解説した10のポイントは、最新のGoogleコアアップデート2025に対応しながら、福岡の企業が競争力を高めるために欠かせない要素を網羅しています。目的設定からターゲット分析、コンテンツ戦略、SEO施策、公開後の改善サイクルまで、一貫した視点で取り組むことで、長期的な成果とブランド価値向上が期待できます。
10のポイントの総括
- 目的設定とKPI設計でゴールを明確化する
- ターゲットユーザー分析でユーザーファースト設計を実現する
- コンテンツ戦略と情報設計でSEOとUXを両立させる
- デザインとUI/UXでブランド体験を強化する
- モバイルファーストで現代の閲覧環境に対応する
- 内部施策で検索エンジンに正しく評価される構造を整える
- 外部施策で信頼性と認知度を向上させる
- セキュリティとパフォーマンスで安心して利用できる環境を提供する
- 分析と改善サイクルで成長を続けるサイト運用を行う
- 適切な制作パートナー選びで長期的な成功を支える
Googleコアアップデート時代のホームページ運用の心得
Googleの評価基準は年々進化し、2025年6月のアップデートでは特にユーザーファーストと文脈整合性が重要視されました。これからのホームページ運用では、単なるキーワード対策ではなく、訪問者の課題解決を中心に据えた情報設計が不可欠です。定期的な分析と改善を繰り返し、ユーザーと検索エンジンの双方に価値を提供し続けることが、長期的な成功への鍵となります。
福岡の企業が成果を出すためには、ホームページとSNSを個別の施策ではなく、ブランド体験全体を設計する起点として捉える視点が欠かせません。株式会社ジャリアでは、検索行動から始まるユーザーファーストの情報設計と、最新のGoogleコアアップデートにも対応したSEO・デジタルブランディング戦略をご提案しています。
ホームページ制作から公開後の運用改善、SNSとの連携まで一貫してサポートすることで、「作って終わり」ではない持続的な集客と認知拡大を実現します。
もし今、ホームページやWEB戦略で課題を感じているなら、まずはお気軽にご相談ください。現状分析から改善提案まで、貴社に最適なプランをご用意いたします。
本記事で解説した内容は、全体戦略の一部に過ぎません。福岡の企業が成果を出すための体系的な取り組みは『福岡企業のためのホームページ制作戦略大全|集客・SEO・ブランド構築』で詳しく紹介しています。